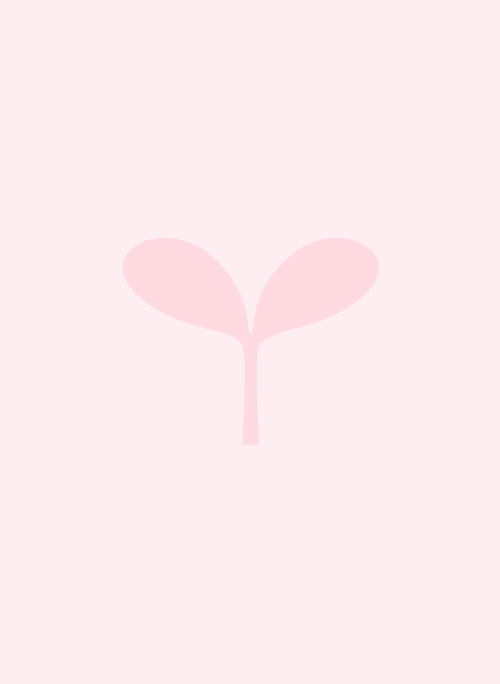そんな事実を揉み消すように
「ご褒美まだだったでしょ?」そう言ってわたしから匠の唇を開く
「ンッ・・」
不意の深いキスに小さな吐息を漏らす匠に、微かな罪悪感を覚える
こんな無垢な少年を、来年の春には無情にもスッパリと切ってしまおうと思う大人のいやらしさを自分に感じる
だけど・・・・
それが堪らなくもある
白い色を纏った匠を汚していく、そんな自分のエロスに自分自身が酔ってしまう
匠とのキスというより、自分の大胆な行為に興奮を覚えて、わたしはいつも匠との交わりを止められない
いや、あの時、彼とこうして交わることが出来たのなら
彼はわたしをどう抱いたのか、わたしにどんな表情を見せたのか
叶わなかった現実を、匠との交わりで埋めようとしている
「ご褒美まだだったでしょ?」そう言ってわたしから匠の唇を開く
「ンッ・・」
不意の深いキスに小さな吐息を漏らす匠に、微かな罪悪感を覚える
こんな無垢な少年を、来年の春には無情にもスッパリと切ってしまおうと思う大人のいやらしさを自分に感じる
だけど・・・・
それが堪らなくもある
白い色を纏った匠を汚していく、そんな自分のエロスに自分自身が酔ってしまう
匠とのキスというより、自分の大胆な行為に興奮を覚えて、わたしはいつも匠との交わりを止められない
いや、あの時、彼とこうして交わることが出来たのなら
彼はわたしをどう抱いたのか、わたしにどんな表情を見せたのか
叶わなかった現実を、匠との交わりで埋めようとしている