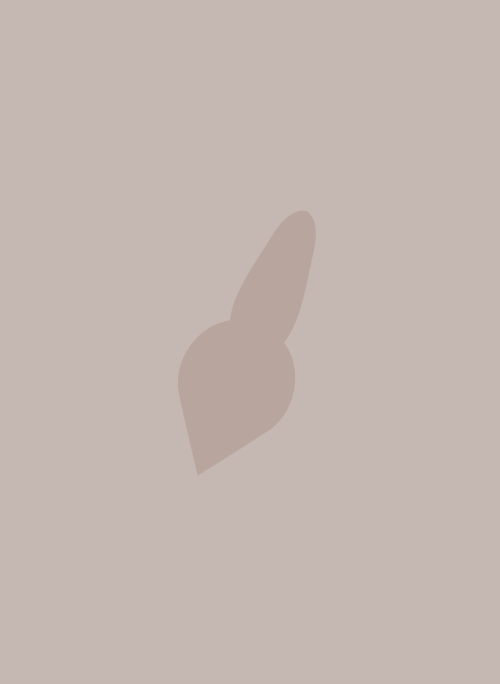死神の爪は『普通』とはかけ離れていた。
「ああ、この爪ですか。或る目的のために伸ばしているんですよ」
その爪は、すらっとした死神の指と同じぐらいの長さだったのだ。
白い部分が、恐ろしい程長い。
「そうですか。じゃあ、少し歩いてきます」
一刻も早く、何も教えてくれそうにない不気味な男から離れたくて、朱理は言葉を発した。
「どうぞ。その代わり、三十分で戻ってきてください。時間の進み方は、現世と一緒ですから。もし、戻らなければ……」
死神の薄い唇が、弧を描く。
「私が連れ戻しますから。力ずくでも」
朱理の背中を、冷たいものが駆け抜けていった。
「ああ、この爪ですか。或る目的のために伸ばしているんですよ」
その爪は、すらっとした死神の指と同じぐらいの長さだったのだ。
白い部分が、恐ろしい程長い。
「そうですか。じゃあ、少し歩いてきます」
一刻も早く、何も教えてくれそうにない不気味な男から離れたくて、朱理は言葉を発した。
「どうぞ。その代わり、三十分で戻ってきてください。時間の進み方は、現世と一緒ですから。もし、戻らなければ……」
死神の薄い唇が、弧を描く。
「私が連れ戻しますから。力ずくでも」
朱理の背中を、冷たいものが駆け抜けていった。