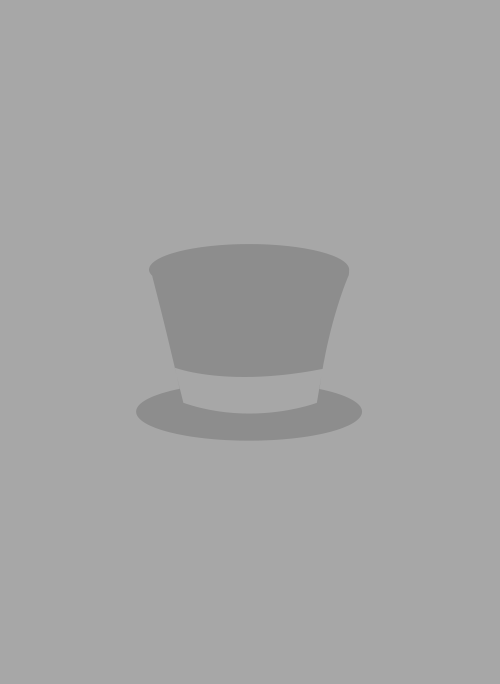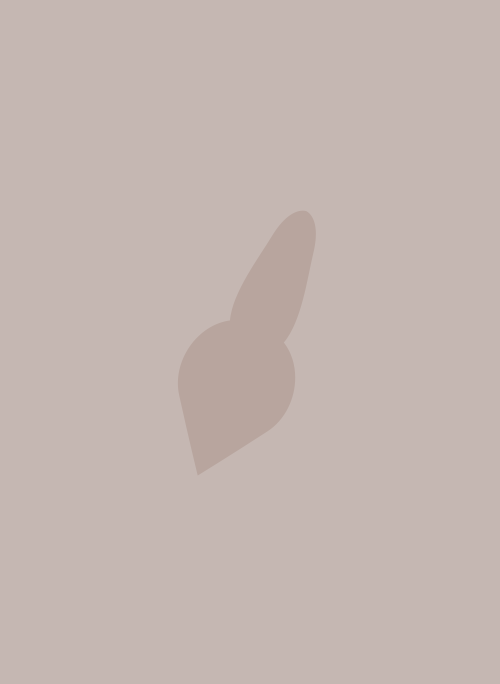朱理が二十一歳になっていた五月上旬のことだ。
病院から帰ってきた朱理は、母がひどく落ち込んでいることに気付いた。
「どうしたの? お母さん」
「さっきまで、おばあちゃんと電話をしていたんだけど、朱理の病気が治らないのはあんたがしっかりしてないからなんじゃないのって言われたの」
胸に、針がずぶり、と刺さる。
「ごめんね、お母さん。私がもっと『普通』の子どもだったら、こんなに苦労することなかったのに……」
心からの、謝罪の言葉だった。
が、母は思わぬ返事をした。
病院から帰ってきた朱理は、母がひどく落ち込んでいることに気付いた。
「どうしたの? お母さん」
「さっきまで、おばあちゃんと電話をしていたんだけど、朱理の病気が治らないのはあんたがしっかりしてないからなんじゃないのって言われたの」
胸に、針がずぶり、と刺さる。
「ごめんね、お母さん。私がもっと『普通』の子どもだったら、こんなに苦労することなかったのに……」
心からの、謝罪の言葉だった。
が、母は思わぬ返事をした。