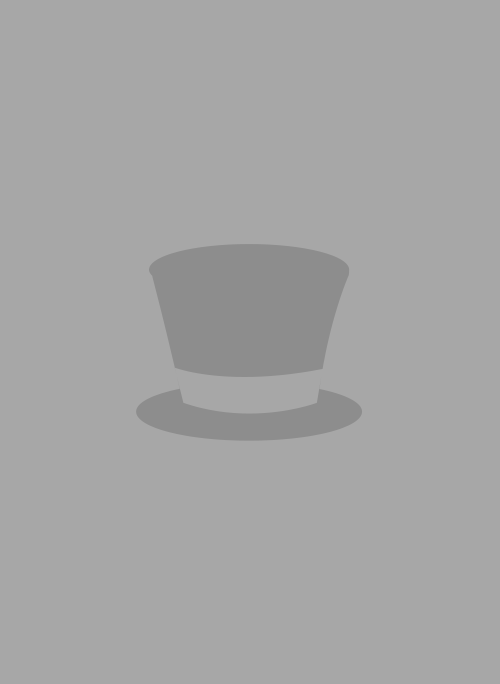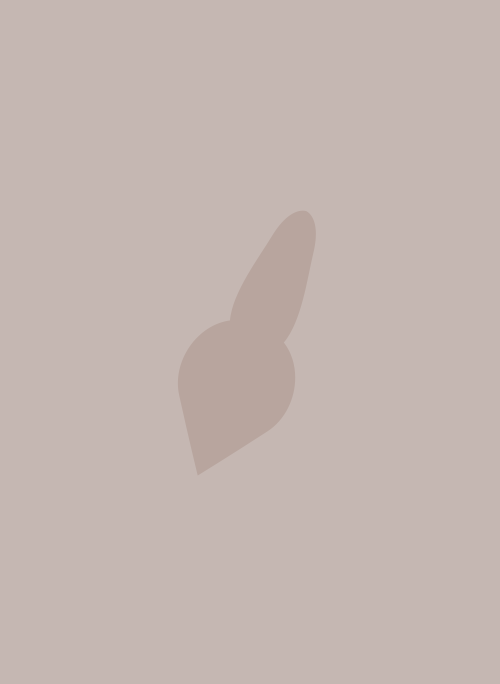「朱理、ごめんね。私、食欲がなくて、夕飯を作る元気がないの。その辺のものを食べてくれる?」
「いいけど。お母さん、大丈夫?」
「うん。ちょっと疲れてるだけ」
朱理が二十歳になった頃から、このようなやり取りが増えていた。
「お母さん、病院にでも行けば?」
「うん。時間があったら行く」
だが、母が病院を訪れることはなかった。
「いいけど。お母さん、大丈夫?」
「うん。ちょっと疲れてるだけ」
朱理が二十歳になった頃から、このようなやり取りが増えていた。
「お母さん、病院にでも行けば?」
「うん。時間があったら行く」
だが、母が病院を訪れることはなかった。