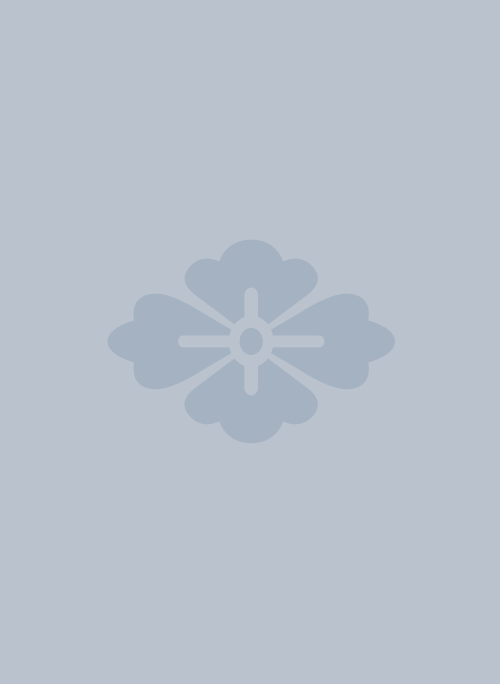「嫁に行っても、ユリは家族だからな。」
お父さんも、こんな感じで私を送り出してくれるのかな。
私を本当の娘のように接してくる王様に、心の中で何度も謝ると、王様の隣をゆっくりと進んでいった。
待っているのは同じく白に身を包んだハリー王子。
じんわりと握りしめた手に汗が滲む。
ハリー王子の隣に立ったとき、ふと目の前の席の人と目が合い、固まった。
その顔はどっからどう見ても船長さんだ!
とてつもない安心感が私を支配する。
「目閉じろ!」
響いた船長さんの声に急いで目を閉じる。
次の瞬間ピカッと周りが光ったと思うと、すぐにまた元に戻った。
「ほら、行くぞ。」
私の汗ばんだ手を握り走り出す船長さん。
周りの人たちは一瞬のこの光に目をやられたらしく、まだ目を押さえている。
同じように目を押さえる王様とお后様を見て、何度も謝りながら私は船長さんと走った。
.