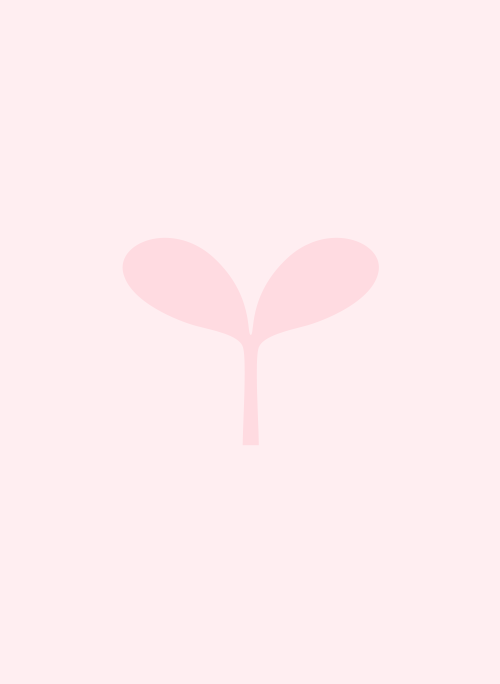呆然自失。
心の準備も何も、あったものじゃない。
ふいに、奪われた。
唇に熱の名残があって、それがただ、現実だったことを知らしめる。
ああ、そういえば9年前もこうやって不意打ちでやられたっけ、とどこか遠くで思い出した。
暗がりでも瞳の奥まで窺えそうな距離で、イノリがあたしを見つめる。
花火を失った手が、イノリの手に捕らえられ、きゅう、と握られた。
「ちゃんと、言っとく。俺、ミャオが好きだ。ずっと傍にいて欲しい」
「あ、の……」
「これからは俺が守る側になりたい。いや、守る側になる。
大事にする、一生。誓うよ」
握ったあたしの左手に、イノリは口を寄せた。
薬指に柔らかくて熱いものが触れる。
けれど瞳はまだ、真っ直ぐにあたしを捉えていた。
「イ、イノ……」
「だから、俺だけ見てて。俺はこれからもずっと、ミャオしか見ない」
逸らさない視線に、全身がどくんと脈打った。
好きとか、ずっととか、一生とか。
イノリはあたしにびっくりするぐらいに大切な言葉をくれる。
びっくりするくらいに、あたしを想ってくれる。
それは、信じられないけど、6歳の、あんなちっちゃな頃から。
「あ、あたしなんか、いいとこない、ぞ?」
情けないくらいに声が震えていた。
だってやっぱり自信が持てない。
想いに応えられるほどの何かが自分にあるなんて言えない。
「口悪いし、がさつだし大ざっぱだし料理もできないし……、それに、イノリと釣り合う見た目じゃない」
思いつくままに言うと、イノリは胸が潰れそうになるくらい、優しく笑った。
「そんなミャオが、俺は世界中の誰よりも好きなんだ」
――どうしたらいいんだろう。
胸が痛くて苦しくて、泣きそうになる。
自信なんて持てない、取り柄のない自分。
たくさんのかわいいや綺麗の中に簡単に埋もれてしまいそうな自分。
こんなにも大切に想われるなんて。
なんて、あたしは幸せなんだろう。
「それに、釣り合う見た目って何だよ。ミャオはすげえかわいいぞ?」
馬鹿だな、とイノリは言う。
そんなこと、あるわけないじゃん。
この顔と何年付き合ってきたと思うんだ。
「イノリって、趣味悪いよ……」
涙は決壊寸前で、それを堪えてぎこちなく笑えば、イノリは空いた方の手であたしの頬に触れた。
頬を包むように、温かな手のひらが重なる。
「そうか? だってほら、こんなにかわいい」
「眼科、行け」
「俺視力いいもん」
イノリの親指が頬をきゅ、と擦る。
その動きに湿り気を感じて、泣いていたことに気が付く。
ギリギリだった涙腺は、既に決壊していたらしい。
心の準備も何も、あったものじゃない。
ふいに、奪われた。
唇に熱の名残があって、それがただ、現実だったことを知らしめる。
ああ、そういえば9年前もこうやって不意打ちでやられたっけ、とどこか遠くで思い出した。
暗がりでも瞳の奥まで窺えそうな距離で、イノリがあたしを見つめる。
花火を失った手が、イノリの手に捕らえられ、きゅう、と握られた。
「ちゃんと、言っとく。俺、ミャオが好きだ。ずっと傍にいて欲しい」
「あ、の……」
「これからは俺が守る側になりたい。いや、守る側になる。
大事にする、一生。誓うよ」
握ったあたしの左手に、イノリは口を寄せた。
薬指に柔らかくて熱いものが触れる。
けれど瞳はまだ、真っ直ぐにあたしを捉えていた。
「イ、イノ……」
「だから、俺だけ見てて。俺はこれからもずっと、ミャオしか見ない」
逸らさない視線に、全身がどくんと脈打った。
好きとか、ずっととか、一生とか。
イノリはあたしにびっくりするぐらいに大切な言葉をくれる。
びっくりするくらいに、あたしを想ってくれる。
それは、信じられないけど、6歳の、あんなちっちゃな頃から。
「あ、あたしなんか、いいとこない、ぞ?」
情けないくらいに声が震えていた。
だってやっぱり自信が持てない。
想いに応えられるほどの何かが自分にあるなんて言えない。
「口悪いし、がさつだし大ざっぱだし料理もできないし……、それに、イノリと釣り合う見た目じゃない」
思いつくままに言うと、イノリは胸が潰れそうになるくらい、優しく笑った。
「そんなミャオが、俺は世界中の誰よりも好きなんだ」
――どうしたらいいんだろう。
胸が痛くて苦しくて、泣きそうになる。
自信なんて持てない、取り柄のない自分。
たくさんのかわいいや綺麗の中に簡単に埋もれてしまいそうな自分。
こんなにも大切に想われるなんて。
なんて、あたしは幸せなんだろう。
「それに、釣り合う見た目って何だよ。ミャオはすげえかわいいぞ?」
馬鹿だな、とイノリは言う。
そんなこと、あるわけないじゃん。
この顔と何年付き合ってきたと思うんだ。
「イノリって、趣味悪いよ……」
涙は決壊寸前で、それを堪えてぎこちなく笑えば、イノリは空いた方の手であたしの頬に触れた。
頬を包むように、温かな手のひらが重なる。
「そうか? だってほら、こんなにかわいい」
「眼科、行け」
「俺視力いいもん」
イノリの親指が頬をきゅ、と擦る。
その動きに湿り気を感じて、泣いていたことに気が付く。
ギリギリだった涙腺は、既に決壊していたらしい。