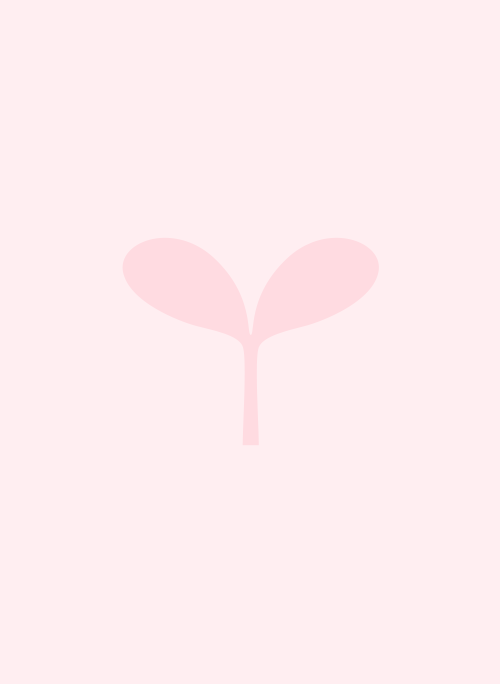「やるやる! あ、このでっかいのあたしやりたい!」
「おう、いいぞ。ほら、こっち」
イノリと並んで、裏庭へと出た。
途中、じいさんの熊のようなイビキが聞こえて、顔を見合わせてこっそり笑った。
「水、用意してくる。ミャオはそこに座って待ってろ。歩き回るなよ」
「うっす。了解!」
案内された裏庭は、こじんまりと整った場所だった。
今は亡きおじいさん(加賀父の実父様だ。二年前にお亡くなりになったらしい。お会いできないままだった。残念)のお部屋の縁側に腰掛ける。
ゆっくり闇に慣れてきた目で見渡せば、隅におかれたプランターから壁に向けて朝顔が蔦を這わせ、朝日に備えて蕾をきゅうと閉じているのが見えた。
お。あんなところにカエルの置物が。
かわいいなあ、誰の趣味だろう。
「お待たせ」
「お……おおう」
イノリがなみなみと水を満たしたバケツを持ってきた。
いや、当たり前のことなんだけど、ちょっと嫌な思い出が蘇っちゃった。
『トイレ用』なんて表記がないか、探しちゃった。
こういうの、トラウマっていうのかねー、早く忘れたいわー。
「どうかしたか?」
「いや、何でもない。花火やろー」
一番でっかい花火を手にして振ってみせると、イノリが笑った。
「おう、いいぞ。ほら、こっち」
イノリと並んで、裏庭へと出た。
途中、じいさんの熊のようなイビキが聞こえて、顔を見合わせてこっそり笑った。
「水、用意してくる。ミャオはそこに座って待ってろ。歩き回るなよ」
「うっす。了解!」
案内された裏庭は、こじんまりと整った場所だった。
今は亡きおじいさん(加賀父の実父様だ。二年前にお亡くなりになったらしい。お会いできないままだった。残念)のお部屋の縁側に腰掛ける。
ゆっくり闇に慣れてきた目で見渡せば、隅におかれたプランターから壁に向けて朝顔が蔦を這わせ、朝日に備えて蕾をきゅうと閉じているのが見えた。
お。あんなところにカエルの置物が。
かわいいなあ、誰の趣味だろう。
「お待たせ」
「お……おおう」
イノリがなみなみと水を満たしたバケツを持ってきた。
いや、当たり前のことなんだけど、ちょっと嫌な思い出が蘇っちゃった。
『トイレ用』なんて表記がないか、探しちゃった。
こういうの、トラウマっていうのかねー、早く忘れたいわー。
「どうかしたか?」
「いや、何でもない。花火やろー」
一番でっかい花火を手にして振ってみせると、イノリが笑った。