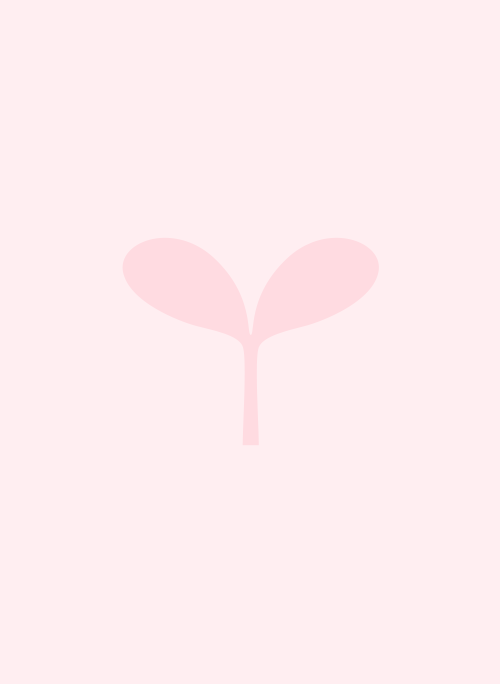イノリに見つけてもらえて、安心したんだ、嗚咽を堪えてそう言うと、イノリは再びあたしを抱きしめた。
「そうだよな、ごめん。もう、大丈夫だから」
温かい手のひらが何度も、背中を往復する。
あたしを落ち着かせようとしてくれているみたいだ。
変なの。
こないだは、あたしがイノリにしてあげてたはずなのに。
少しこそばゆい。でも、嫌じゃない。
しばらくして、イノリがあたしを離して顔を覗き込んだ。
「もう、平気か?」
「ん」
いつの間にか、涙も止まっていた。
頷くと、ほっとしたように笑ったイノリはあたしの背の赤土の壁を見やった。
「ここから落ちたのか? 痛いとこあるか?」
「あ、え、と。左、足」
「こっち?」
イノリがあたしの足元に懐中電灯を向けた。
照らされた足首は、予想通り、腫れ上がっていた。
「折れてるのか?」
「いや、捻挫」
「あとは?」
「擦り傷、くらい」
「ここか。ああ、血が出てる。後は平気か?」
眉間に皺をよせながらあたしの体をチェックする。
「よし。足、くらいだな。ここにはあの看板みて、入ったのか」
「うん。おかしいな、とは思ったんだけど……」
「誰かの悪戯だろうが、危ねえな。撤去した方がいいかもな」
苦々しく言ったイノリは、ケータイを取り出した。
誰かにかけているらしい、小さくコール音がした。
「もしもし、オヤジ? ああ、ミャオ見つけた。やっぱ山ん中だった。うん……うん、そう、あのケータイが落ちてた山道の奥……、そう」
電話の相手は加賀父らしい。
もしかして、加賀父もあたしを探してくれてた、とかだろうか。
「織部のじいさんにも連絡しといて。で、ミャオ怪我してる。……うん、捻挫。うん、今から連れて帰る」
織部のじいさんまでも?
どうしよう、まさか大きな話になっているんじゃないだろうか。
あたしの勝手な行動で、多くの人に迷惑をかけたんだ。
馬鹿だ、あたし。どうやって謝ったらいいんだろう。
「あ、あの。ごめん」
通話を終えたイノリに謝る。
「そうだよな、ごめん。もう、大丈夫だから」
温かい手のひらが何度も、背中を往復する。
あたしを落ち着かせようとしてくれているみたいだ。
変なの。
こないだは、あたしがイノリにしてあげてたはずなのに。
少しこそばゆい。でも、嫌じゃない。
しばらくして、イノリがあたしを離して顔を覗き込んだ。
「もう、平気か?」
「ん」
いつの間にか、涙も止まっていた。
頷くと、ほっとしたように笑ったイノリはあたしの背の赤土の壁を見やった。
「ここから落ちたのか? 痛いとこあるか?」
「あ、え、と。左、足」
「こっち?」
イノリがあたしの足元に懐中電灯を向けた。
照らされた足首は、予想通り、腫れ上がっていた。
「折れてるのか?」
「いや、捻挫」
「あとは?」
「擦り傷、くらい」
「ここか。ああ、血が出てる。後は平気か?」
眉間に皺をよせながらあたしの体をチェックする。
「よし。足、くらいだな。ここにはあの看板みて、入ったのか」
「うん。おかしいな、とは思ったんだけど……」
「誰かの悪戯だろうが、危ねえな。撤去した方がいいかもな」
苦々しく言ったイノリは、ケータイを取り出した。
誰かにかけているらしい、小さくコール音がした。
「もしもし、オヤジ? ああ、ミャオ見つけた。やっぱ山ん中だった。うん……うん、そう、あのケータイが落ちてた山道の奥……、そう」
電話の相手は加賀父らしい。
もしかして、加賀父もあたしを探してくれてた、とかだろうか。
「織部のじいさんにも連絡しといて。で、ミャオ怪我してる。……うん、捻挫。うん、今から連れて帰る」
織部のじいさんまでも?
どうしよう、まさか大きな話になっているんじゃないだろうか。
あたしの勝手な行動で、多くの人に迷惑をかけたんだ。
馬鹿だ、あたし。どうやって謝ったらいいんだろう。
「あ、あの。ごめん」
通話を終えたイノリに謝る。