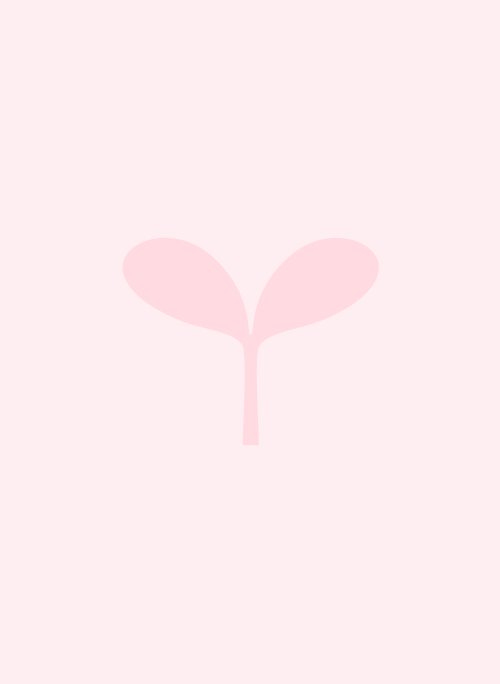「オレは、やっぱり大澤は美弥緒が好きなんじゃないかと思うんだよね」
「あたしもそう思う! やっぱりそうだよねえ」
「それ以外理由が思いつかないよね」
「だーかーらー、それはないって」
盛り上がる二人に水を差すようで悪いが、そこはきっちり否定させてもらう。
「なんで? 可能性として否定できないよ?」
「さっきも言ったけど、大澤はあたしを誰かと勘違いしてるだけなんだよ。
今日のいざこざの時も、俺の知ってるお前じゃない、みたいなこと言われたし」
お前の知ってる『あたし』って、どんなんだよ、ってね。
ひょいと肩を竦めてみせると、穂積は考え込むようにううん、と唸った。
「勘違い、で済む話なのかなー。だって入学してもう3ヶ月だよ?
大澤は毎日のように君を見てるんだから、人違いならいい加減気がつくと思うんだけどな」
「とは言われても。記憶なんて、ないんだよ」
「うん。美弥緒の言ってることが嘘だと思ってるわけじゃない。どこかで、ズレがあるんだろうな」
「ズレ、ねえ」
確かに、大澤が鈍い人間だと仮定しても、そろそろ人違いだと気付いてもよさそうなもんだ。
いくらあたしがそこいらにありがちな容姿だとしても、同じ顔の人間がたくさんいるわけじゃないしね。
「うー、ん。ありえないとは思うけど、とりあえず、親に訊いてみようかな」
9年前のK駅、だったよね。
もしかしたらあたしがすっぽり忘れているだけで、行ったことがあるのかもしれないし。
だとしたら、何か思い出すのかも。
「そうだね。確認してみたらどうかな?」
「うん。なにかわかったら穂積にも報告するよ」
「うん。ありがとう」
「じゃあ、そろそろ帰ろっか。明日、早いしね」
話が落ち着いたところで、琴音が言った。
そうだ。あたしは人よりも更に30分早いんだった。
鳴沢様の録画予約の確認や、荷物の確認もしなくちゃいけないし。
「よし、帰ろう。じゃあ、今日もお疲れさまでした!」
「ああ、お疲れさま。明日は、楽しく頑張ろうね」
「うん」
慌しく教室を後にした。
「あたしもそう思う! やっぱりそうだよねえ」
「それ以外理由が思いつかないよね」
「だーかーらー、それはないって」
盛り上がる二人に水を差すようで悪いが、そこはきっちり否定させてもらう。
「なんで? 可能性として否定できないよ?」
「さっきも言ったけど、大澤はあたしを誰かと勘違いしてるだけなんだよ。
今日のいざこざの時も、俺の知ってるお前じゃない、みたいなこと言われたし」
お前の知ってる『あたし』って、どんなんだよ、ってね。
ひょいと肩を竦めてみせると、穂積は考え込むようにううん、と唸った。
「勘違い、で済む話なのかなー。だって入学してもう3ヶ月だよ?
大澤は毎日のように君を見てるんだから、人違いならいい加減気がつくと思うんだけどな」
「とは言われても。記憶なんて、ないんだよ」
「うん。美弥緒の言ってることが嘘だと思ってるわけじゃない。どこかで、ズレがあるんだろうな」
「ズレ、ねえ」
確かに、大澤が鈍い人間だと仮定しても、そろそろ人違いだと気付いてもよさそうなもんだ。
いくらあたしがそこいらにありがちな容姿だとしても、同じ顔の人間がたくさんいるわけじゃないしね。
「うー、ん。ありえないとは思うけど、とりあえず、親に訊いてみようかな」
9年前のK駅、だったよね。
もしかしたらあたしがすっぽり忘れているだけで、行ったことがあるのかもしれないし。
だとしたら、何か思い出すのかも。
「そうだね。確認してみたらどうかな?」
「うん。なにかわかったら穂積にも報告するよ」
「うん。ありがとう」
「じゃあ、そろそろ帰ろっか。明日、早いしね」
話が落ち着いたところで、琴音が言った。
そうだ。あたしは人よりも更に30分早いんだった。
鳴沢様の録画予約の確認や、荷物の確認もしなくちゃいけないし。
「よし、帰ろう。じゃあ、今日もお疲れさまでした!」
「ああ、お疲れさま。明日は、楽しく頑張ろうね」
「うん」
慌しく教室を後にした。