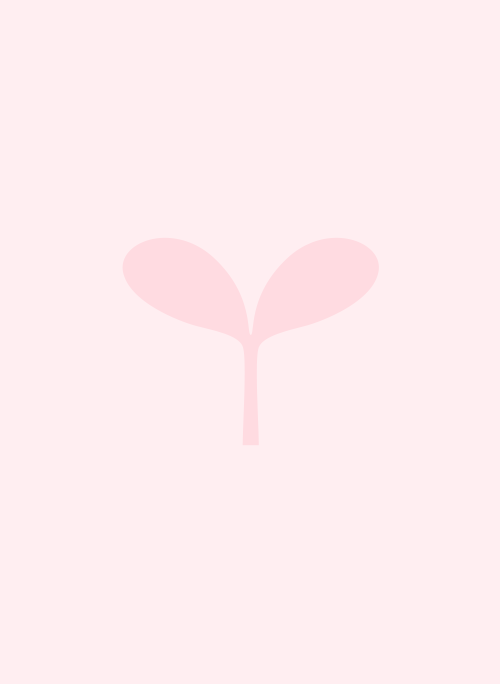穂積と大澤は、小学校五年のころからずっと同じクラスだったのだそうだ。
穂積はそのときから、大澤を意識していたのだという。
「自分で言うのもおこがましいんだけどね、オレ、すごくモテてたんだ。
でもね、大澤と同じクラスになってからは、人気が落ちたんだよね。
女の子が人気投票みたいなことやると、オレはいつも大澤の下になっちゃうわけ。やっぱり少し悔しくなっちゃうんだよね」
ライバル、というやつですか。
青春だねー。いいよいいよ、そういうのって文部科学省も推奨してるからね、多分。
しかし、そこから熱い展開になるわけではなかった。
同じクラスが続いても、2人は争うわけでもなく、はたまた親しくなるでもなかった。
単なるクラスメイトとして、時間を過ごしてきたそうだ。
まあ、そんなもんよね、現実は。
穂積も大澤が気になって仕方がない、というほどでもなかった。
人気が落ちたといっても、全くなくなったわけではなく、
元来女の子が好きでもあるし(うん、やっぱりね、って感じ)、彼女とかほどよく作って楽しんでいたらしい。
が。
「大澤の方はさ、女の子に全然全くもう無関心。どんな子が迫ってもお断りしてさー。
信じられなかったよ」
あんなに綺麗な見た目を持っているのに、今まで特定の女の子を作ったりなどしなかったらしい。
「不思議じゃない?
健全な男子は、自分に好意を持ってくれているかわいらしい無防備な女の子を目の前にしておいて、『ごめんね』なんて言えないんだよね。好奇心が左右する年頃だからさー。色んな味を知りたいはずなんだよね」
……穂積さん、意外に貪欲なんですね。
こういうのもグルメって言っていいんでしょうか。
心底理解できない、という風に語る穂積に、琴音と二人でふむふむと相槌を打つ。
「でも、どんな子でも大澤は絶対断るんだ。
中学の先輩にさ、すごく綺麗な人がいたんだよね。高嶺の花、っていうやつ? 医者の家系のお嬢様で、しかも文武両道。
その子が捨て身で告白しても、大澤はあっさり断ったんだって」
ほほう。
そりゃ、あれじゃないかい。
趣味が悪いってやつ。
それか、BLかな。あたしのイチオシはもちろんBLですけど。
「もしかして女に興味がなくて、男が好きなんじゃないか、なんて話もでたんだけどね」
だよねー、そうだよね。そこにいっちゃうよね。
恋愛に縛りはないんだし、問題ないよ。
「でも、特定の友人もいなかったし、男には優しいってわけでもないし、そういう可能性はないだろうってことになったけどさ」
そうなんだー。残念。
って、別にBLがすごく好きというわけじゃないけどね。
でも大澤と穂積だったらなんていうか、耽美だしさ。
見てみたいなー、という好奇心。
「そんな大澤がさ、初めて女の子に興味を示してる。呼び名にまで執着してる。
これは、面白いといってもいいんじゃない?」
「そうだねえ。そういう流れだと、確かに」
こくこくと頷く琴音に、穂積が続けた。
穂積はそのときから、大澤を意識していたのだという。
「自分で言うのもおこがましいんだけどね、オレ、すごくモテてたんだ。
でもね、大澤と同じクラスになってからは、人気が落ちたんだよね。
女の子が人気投票みたいなことやると、オレはいつも大澤の下になっちゃうわけ。やっぱり少し悔しくなっちゃうんだよね」
ライバル、というやつですか。
青春だねー。いいよいいよ、そういうのって文部科学省も推奨してるからね、多分。
しかし、そこから熱い展開になるわけではなかった。
同じクラスが続いても、2人は争うわけでもなく、はたまた親しくなるでもなかった。
単なるクラスメイトとして、時間を過ごしてきたそうだ。
まあ、そんなもんよね、現実は。
穂積も大澤が気になって仕方がない、というほどでもなかった。
人気が落ちたといっても、全くなくなったわけではなく、
元来女の子が好きでもあるし(うん、やっぱりね、って感じ)、彼女とかほどよく作って楽しんでいたらしい。
が。
「大澤の方はさ、女の子に全然全くもう無関心。どんな子が迫ってもお断りしてさー。
信じられなかったよ」
あんなに綺麗な見た目を持っているのに、今まで特定の女の子を作ったりなどしなかったらしい。
「不思議じゃない?
健全な男子は、自分に好意を持ってくれているかわいらしい無防備な女の子を目の前にしておいて、『ごめんね』なんて言えないんだよね。好奇心が左右する年頃だからさー。色んな味を知りたいはずなんだよね」
……穂積さん、意外に貪欲なんですね。
こういうのもグルメって言っていいんでしょうか。
心底理解できない、という風に語る穂積に、琴音と二人でふむふむと相槌を打つ。
「でも、どんな子でも大澤は絶対断るんだ。
中学の先輩にさ、すごく綺麗な人がいたんだよね。高嶺の花、っていうやつ? 医者の家系のお嬢様で、しかも文武両道。
その子が捨て身で告白しても、大澤はあっさり断ったんだって」
ほほう。
そりゃ、あれじゃないかい。
趣味が悪いってやつ。
それか、BLかな。あたしのイチオシはもちろんBLですけど。
「もしかして女に興味がなくて、男が好きなんじゃないか、なんて話もでたんだけどね」
だよねー、そうだよね。そこにいっちゃうよね。
恋愛に縛りはないんだし、問題ないよ。
「でも、特定の友人もいなかったし、男には優しいってわけでもないし、そういう可能性はないだろうってことになったけどさ」
そうなんだー。残念。
って、別にBLがすごく好きというわけじゃないけどね。
でも大澤と穂積だったらなんていうか、耽美だしさ。
見てみたいなー、という好奇心。
「そんな大澤がさ、初めて女の子に興味を示してる。呼び名にまで執着してる。
これは、面白いといってもいいんじゃない?」
「そうだねえ。そういう流れだと、確かに」
こくこくと頷く琴音に、穂積が続けた。