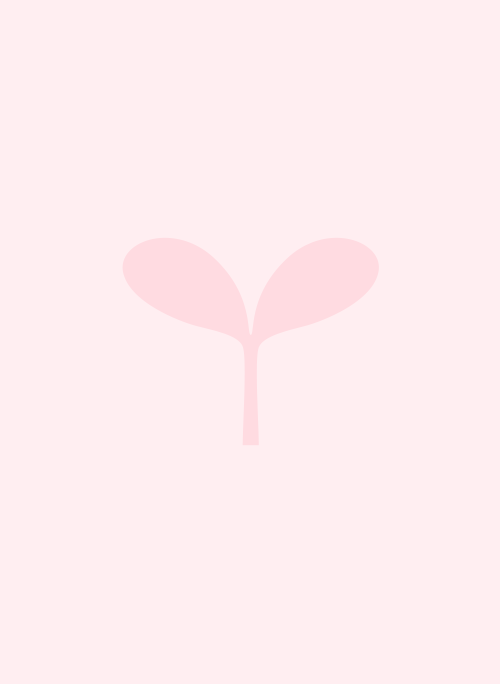必死になってほぼ叫ぶように言うと、ようやく腕が緩んだ。
しかしそれはほんの少し力を抜いた程度で、あたしの頬は相変わらずイノリの胸元にあった。
「ちょ、離れてってば!」
聞きたいことが聞けたっていうんなら、もういいよね!?
ぐいぐいと押すのだが、離れてくれない。
つーか、こんなに力込めてやってんのに、何でびくともしないの?
え、男ってこんなに力あんの?
「……嫌。離したくない」
「なんだよそれ! つーか摺り寄ってくんな!」
頭にすり、と頬を寄せてくる感覚があった。
「ミャオの匂いがする。つーかミャオ、膝に乗れ。そっちのがいい」
「馬鹿か!! 乗るわけねーだろ! 離せっつってんだ!」
ぎゃいぎゃいと暴れるあたしにお構いなしに、イノリは頭に顔を寄せ、すりすりしている。
「嫌。やっとホントのミャオに会えたのに、離れる意味がわかんねーし」
「意味わかんねーのはオマエだっつの!」
まるで大型犬がもっふもっふと懐いてくるかのようだ。
って、犬だったらいいけど、イノリだしな! しかもでかい方ときた。
6歳のイノリならこっちだってよしよしと撫でてやるよ! と文句の合間に言うと、
「ああ、撫でるのはいらない。ガキのときも、俺がミャオをこうしたかったんだ」
と、大型犬がのたまった。
「はぁ!? どんだけマセてんだよ! 末恐ろしいな!」
「そうか? ああ、やっぱまだ遠い。もっとこっち来て」
縛っていた腕が離れ、背中と膝裏にすいとイノリの手が触れた。
と思った次の瞬間、ひょいと抱え上げられた。
「ぎゃ!?」
ふわりと浮いた体は、イノリの膝上に着地した。
ぐんと顔が近づいて、あたしを乗せた男は満足そうに笑った。
「うん、とりあえずはこれでいい」
「な、な……」
何してくれとんじゃ、この馬鹿!
離れんかい、ワレ!
等々と言いたいのだが、驚きの余り口はパクパクと動くだけで、声がでない。
つーか今、あたしってイノリの膝の上ってところにいるわけ?
抱っこ、みたいな?
ナイナイナイナイ。
ムリムリムリムリ。
もうついていけない。
「あ、あ、あう」
「どうした?」
しかしそれはほんの少し力を抜いた程度で、あたしの頬は相変わらずイノリの胸元にあった。
「ちょ、離れてってば!」
聞きたいことが聞けたっていうんなら、もういいよね!?
ぐいぐいと押すのだが、離れてくれない。
つーか、こんなに力込めてやってんのに、何でびくともしないの?
え、男ってこんなに力あんの?
「……嫌。離したくない」
「なんだよそれ! つーか摺り寄ってくんな!」
頭にすり、と頬を寄せてくる感覚があった。
「ミャオの匂いがする。つーかミャオ、膝に乗れ。そっちのがいい」
「馬鹿か!! 乗るわけねーだろ! 離せっつってんだ!」
ぎゃいぎゃいと暴れるあたしにお構いなしに、イノリは頭に顔を寄せ、すりすりしている。
「嫌。やっとホントのミャオに会えたのに、離れる意味がわかんねーし」
「意味わかんねーのはオマエだっつの!」
まるで大型犬がもっふもっふと懐いてくるかのようだ。
って、犬だったらいいけど、イノリだしな! しかもでかい方ときた。
6歳のイノリならこっちだってよしよしと撫でてやるよ! と文句の合間に言うと、
「ああ、撫でるのはいらない。ガキのときも、俺がミャオをこうしたかったんだ」
と、大型犬がのたまった。
「はぁ!? どんだけマセてんだよ! 末恐ろしいな!」
「そうか? ああ、やっぱまだ遠い。もっとこっち来て」
縛っていた腕が離れ、背中と膝裏にすいとイノリの手が触れた。
と思った次の瞬間、ひょいと抱え上げられた。
「ぎゃ!?」
ふわりと浮いた体は、イノリの膝上に着地した。
ぐんと顔が近づいて、あたしを乗せた男は満足そうに笑った。
「うん、とりあえずはこれでいい」
「な、な……」
何してくれとんじゃ、この馬鹿!
離れんかい、ワレ!
等々と言いたいのだが、驚きの余り口はパクパクと動くだけで、声がでない。
つーか今、あたしってイノリの膝の上ってところにいるわけ?
抱っこ、みたいな?
ナイナイナイナイ。
ムリムリムリムリ。
もうついていけない。
「あ、あ、あう」
「どうした?」