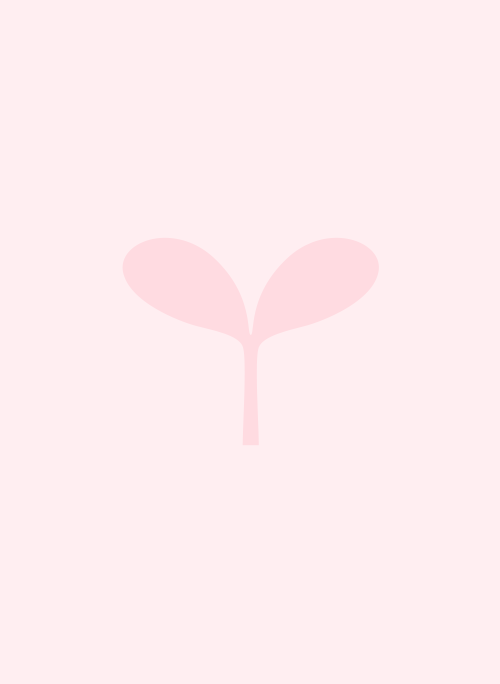「なんだ、そんなの。いいよ。いっぱい『りし』つけといてよ」
「いてて……。お、本当にいいのかい? ぐへへ、ありがとよ」
「なんだか悪い笑い方になってるよ、ミャオ……」
「うるさい。あ、そうだ。これ、足に張っておきな」
救急箱から湿布をとりだして、イノリに渡した。
「ホントは貼ってやりたいんだけど、ごめん。自分でできる?」
「ん。でもミャオも貼りなよ。ミャオも痛いでしょ」
「はは、了解。あ、こっちはお茶とおにぎり。食べな?」
「ありがとう」
揺れる車内で、んしょんしょ、と湿布を張る。
うへー。ひやっこい。でも気持ちいーかも。
腫れたところが熱をもっててうずいてたからなー。
「だいぶ明るくなってきたなー、ほら、朝日」
巧みなハンドル捌きをみせる加賀父が窓の向こうを指差した。
「あ、ほんとだ……」
峰の間から、太陽が顔を覗かせていた。
9年前の世界で2回目の朝だ。
木々を照らし、ゆっくり上る太陽。
普段日の出なんてみないから、少し珍しさを感じてしまう。
雲もないし、今日もびっくりするくらい暑い一日になるんだろう。
しかし、爽やかな気分には到底なれなかった。
逆に、深く落ち込んでいった。
あの太陽が沈むころ、あたしはどこにいるんだろう。
ちゃんと、9年後にいて、9年後の日の入りを見られるのだろうか。
やっぱり帰れなくて、ここで帰る方法を模索しているんじゃないだろうか。
ざわりと足が竦んだ。
車載時計の表示は、5時32分。
2時間後、あたしはK駅前のバス停にいる?
なにより無事に戻れる?
『帰れるのか』、ということが、今更になって心に重くのしかかってきた。
加賀父の言葉以外、元に帰れるという保障はどこにもない。
こうしてバス停に向かっても、7時45分をこの時代で過ごしてしまうかもしれないのだ。
「美弥緒ちゃん、少し眠りなさい」
「え!?」
無意識にぎゅうと握り締めていた手がふわりと包み込まれた。
「一晩寝てないんだ。疲れてるだろう? 疲れは心を侵食してしまうから、休みな」
「い、いいいいいや、その、あの」
ぎゃー!
金吾様に手を! 手を!
「心配しなくてもいい。君は必ず、俺が帰すから」
「で、でも……」
「絶対、だから」
ぎゅ、と力が込められた。
「いてて……。お、本当にいいのかい? ぐへへ、ありがとよ」
「なんだか悪い笑い方になってるよ、ミャオ……」
「うるさい。あ、そうだ。これ、足に張っておきな」
救急箱から湿布をとりだして、イノリに渡した。
「ホントは貼ってやりたいんだけど、ごめん。自分でできる?」
「ん。でもミャオも貼りなよ。ミャオも痛いでしょ」
「はは、了解。あ、こっちはお茶とおにぎり。食べな?」
「ありがとう」
揺れる車内で、んしょんしょ、と湿布を張る。
うへー。ひやっこい。でも気持ちいーかも。
腫れたところが熱をもっててうずいてたからなー。
「だいぶ明るくなってきたなー、ほら、朝日」
巧みなハンドル捌きをみせる加賀父が窓の向こうを指差した。
「あ、ほんとだ……」
峰の間から、太陽が顔を覗かせていた。
9年前の世界で2回目の朝だ。
木々を照らし、ゆっくり上る太陽。
普段日の出なんてみないから、少し珍しさを感じてしまう。
雲もないし、今日もびっくりするくらい暑い一日になるんだろう。
しかし、爽やかな気分には到底なれなかった。
逆に、深く落ち込んでいった。
あの太陽が沈むころ、あたしはどこにいるんだろう。
ちゃんと、9年後にいて、9年後の日の入りを見られるのだろうか。
やっぱり帰れなくて、ここで帰る方法を模索しているんじゃないだろうか。
ざわりと足が竦んだ。
車載時計の表示は、5時32分。
2時間後、あたしはK駅前のバス停にいる?
なにより無事に戻れる?
『帰れるのか』、ということが、今更になって心に重くのしかかってきた。
加賀父の言葉以外、元に帰れるという保障はどこにもない。
こうしてバス停に向かっても、7時45分をこの時代で過ごしてしまうかもしれないのだ。
「美弥緒ちゃん、少し眠りなさい」
「え!?」
無意識にぎゅうと握り締めていた手がふわりと包み込まれた。
「一晩寝てないんだ。疲れてるだろう? 疲れは心を侵食してしまうから、休みな」
「い、いいいいいや、その、あの」
ぎゃー!
金吾様に手を! 手を!
「心配しなくてもいい。君は必ず、俺が帰すから」
「で、でも……」
「絶対、だから」
ぎゅ、と力が込められた。