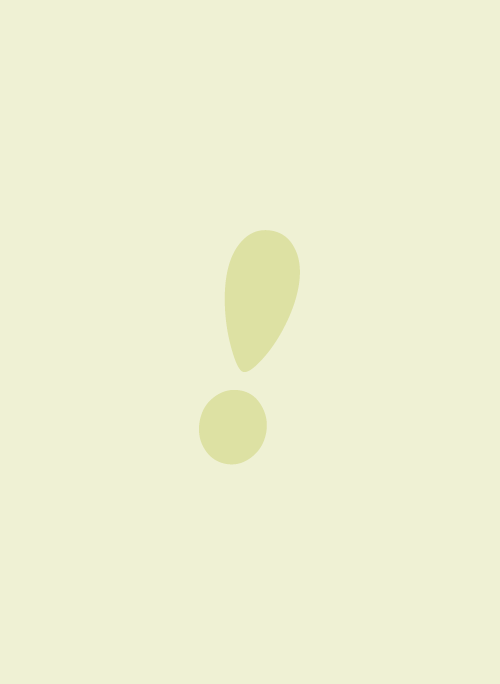部室の雰囲気は、最悪だ。
誰も話そうとしない。時々、ため息をつきながら自分の仕事をこなすだけ。
その中で、隣の恵梨がさっきから頻繁に顔に手をやっていた。泣いているのだと分かった。
大好きな部長にビンタを食らったことが、ショックだったのだろう。
かわいそうになってティッシュを差し出したけれど、恵梨は頑なに受け取ろうとしない。
「いらない!そんなの」
ぶっきらぼうな言葉に、さっきのトイレの会話を思い出した私は思わず、手を引っ込めてしまった。
恵梨は自分で出したハンカチで涙を拭きながら、
「ったく、なんで私まで叩かれんのよ?」
そうつぶやいた。
『なんで、私まで』
その言葉の中に、
あんたが素直に非を認めていれば、あんた一人が罰を受ければ済むことだったのに。
という、言外の意味が込められていることに気づくのに、そう時間はかからなかった。
そして、それを否定する人は誰もいなかった。
ばんび、あんた一人が罰を受ければよかったのに。
みんな、そう思っているんだ。
部屋中の空気が針のように尖って、体中にささってくるような錯覚を覚える。
私はその痛みに、無言で耐えるしかなかった。