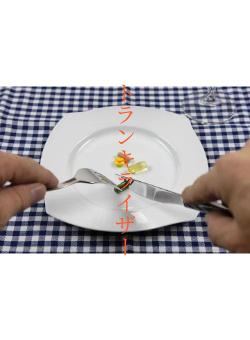私は彼女たちの姿が見えなくなってから、お墓に近寄った。左之はじっとお墓を見つめていた。
「居た?」
「いや、居ない」
「そっか」
「でも、ここは温かいな。何人もの人間のぬくもりを感じる」
「うん」
左之も同じことを思っていたんだろう。彼女たちの存在が嬉しかったはずだ。
「自分たちの死後、こんな風に弔ってくれるものがいるというだけで、きっと近藤さん、号泣してるだろうな。幸福者だ」
ハハッと左之は嬉しそうに笑った。
「左之、私もこの辺掃除してくるから、ここでゆっくりしてて」
「でもさっきの子達がしてたんだろう?」
「いいの、あるかもしれないでしょ」
何か役に立ちたい、そう思った。