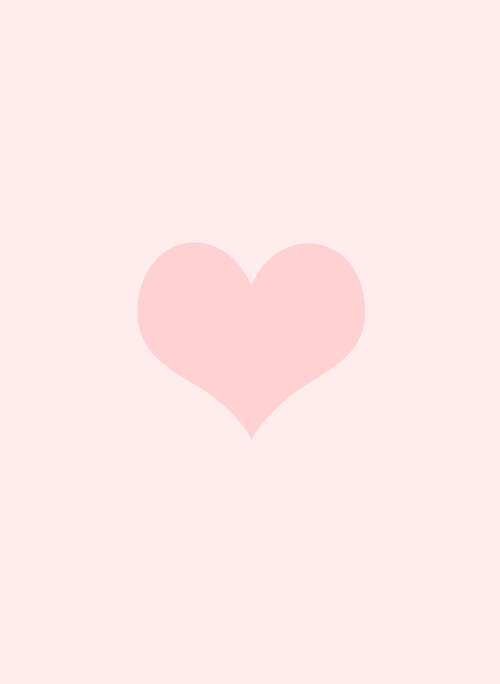「ああっ、あー、あうーっ」
「…………」
揺りかごに入れられてしきりに喘ぐ幼い子供。
この光景を哀れと思うのは、揺りかごの周りが地獄のように真っ赤で……子供の両親がぐったりと絨毯に倒れているからだ。
暗い屋敷の中で、煩わしく喚くその子に感じたのは雑じり気の無い嫌悪。
どうせ焼かれてしまうのだから、いっそこの場で苦しまないよう喉元を刺してやった方が良心的なんじゃないか――…。
「子供まであっさり殺そうとするんですか」
「………アル」
赤子の喉元に剣の刃を押し当ててすぐ、背後から呆れたらしいため息が聞こえた。
「あっさりとは、人聞きが悪いな」
「でも罪悪感の欠片もなかったでしょ、今」
うなずかざるを得ない。
この時、この俺という男は赤子に対してどういう始末を付けるか、しか対処法の選択肢はなかった。
だって当然のこと。
一家もろとも消し去るのは俺の一種の礼儀と考えていたからだ。
消すべき対象は必ず一家の大黒柱。
残されるより一緒に消えた方がいい。