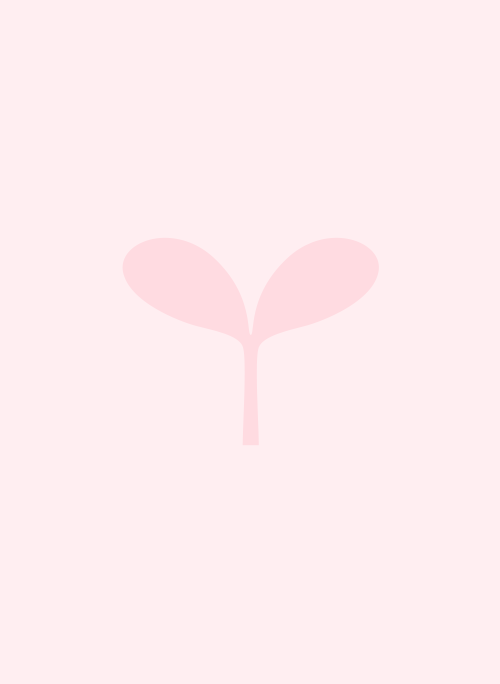街から離れた、廃家が建つ丘の上。
プラチナブロンドの髪を靡かせながら、一人の少女は夕焼け空を眺めていた。
ふと彼女の後ろに、黒い霧が集まる。
その中から、一人の少年が姿を現した。
ディオンは微笑みながら、セリシアの隣に行く。
茜色の空が紫紺(しこん)に染まっていくのを、ただ静かに、眺め続けた。
ぎゅ、とお互いの手を握る。
「もう少しだね。……もう少しで、この世界からは人間が消え、そして僕らも、人工精霊と共に消える」
呟きながら、セリシアはディオンの肩に頭を添える。
〝不安〟という思いが、ディオンの心に伝わった。
「僕がずっと、君の傍にいるよ」
それが僕の願いであり、また君の願いでもあるから――。
「……ディオン。あの二人を、殺さなかったんだね」
す、とディオンは目を伏せる。強く、唇を噛み締めていた。
見るも無残なほどに、殺してやりたかった。
けれどセリシア、君があのとき……。
「ディオン? どうかした?」
黙り込んだのを不思議に思ったのか、セリシアは顔を覗き込む。
何でもないよ、とディオンは微笑み、殺す気が失せたのさ、と偽りの言葉を述べた。
紺碧(こんぺき)に染まった空に、壮麗な満月が浮かぶ。
次第に月が欠けはじめた、そのときだった。
「ディオン、セリシア!」
聞き慣れた声が、耳に入った。