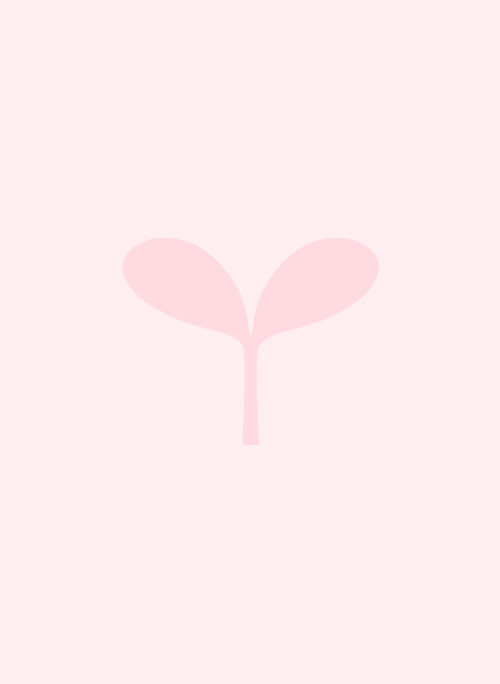「そんなことが……」
アンネッテは胸を締めつけられたような思いになる。
「闇獣に襲われた恐怖と、目の前で傷を負った彼女の姿を見たショックを受け、子どもの儚い心は、いとも簡単に壊れたさ」
恐怖によって体を震わせ、顔を真っ青にしながら、泣いていた。
彼だって、本当は泣きたかった。
それでも必死に悲しみを堪え、慰めるために、その子に触れようとした。
けれどその手は払い除けられた。
今までずっと傍にいた彼にですら、恐怖心を持ってしまったのだ。
そして彼は、その子がこれ以上苦しまないように――。
「僕は力を使い、人の子の記憶を消したんだ。彼女のことや僕のことはもちろん、一緒に過ごしてきた記憶も、全て。それから、子どものいなかった夫婦のもとへ連れて行き、その夫婦の記憶も変えた。そしてあたかもそこで生まれ育ったかのように、偽りの記憶を人の子に与えたのさ」
誰かの記憶を消すことも、変えることも、自らの命を対価としなければならないため、禁忌とされている。
けれど彼はそれを知っていて、人の子のために、禁忌を破った。
そして、消えてしまった。
「精霊だったとき、僕は確かに人間のことを嫌ってはいなかった。むしろ好きな方だったんだよ」
でも、とディオンは続ける。
「精霊使いとして誕生してからは、人間が憎たらしくて仕方がないんだ。だって人間は、僕の愛しいセリシアから、笑顔を奪ったんだもの」
とても愛しい、僕のセリシア。
けれど一部の感情を奪われ、笑ったことがある記憶すらも失ってしまった、悲哀なる僕の妹。