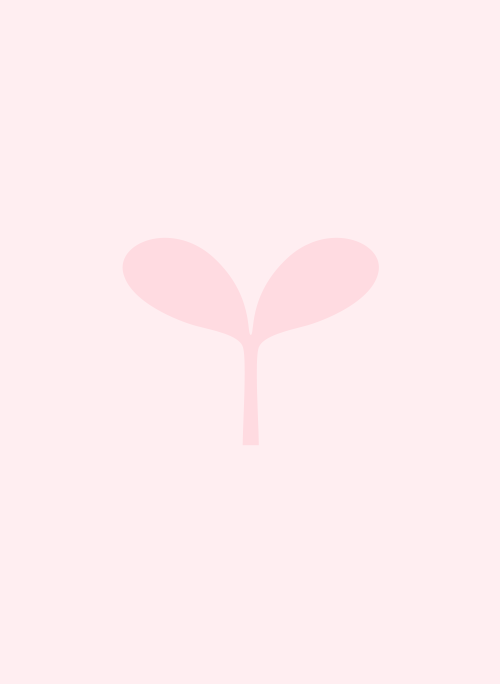「そうだね。奴らに見つかってしまう前に、行かないと……」
もう動かせない、と悲鳴を上げる足を無理やり動かしながら、二人は再び走り出す。
生まれて初めて目にした朝陽を、じっくりと眺めている暇などはなかった。
〝奴らのもとになんて、戻りたくない〟――ただ何度も何度も胸の内で叫び続け、そしてレクスを、憎んだ。
「もう、少し……」
ようやく丘を上るという所まで来たとき、二人の体力はすでに限界を超えていた。
捕まりたくない、という気力だけで足を動かし続けたが、それすらも、もう限界だった。
ふらりと一人がその場に倒れる。先に倒れたのは、セリシアだ。
「セリシア、セリシア!」
必死の呼び掛けに、うっすらと彼女は目を開ける。立ち上がろうと試みるが、体に力が入らなかった。
セリシアは、僕が守るんだ。
ぐっと力を込め、セリシアを背負う。
僅かに震える足で、少しずつ、けれど確実に、赤い屋根の家へと近付いて行く。
目の前が霞(かす)もうと、必死に進み続けた。