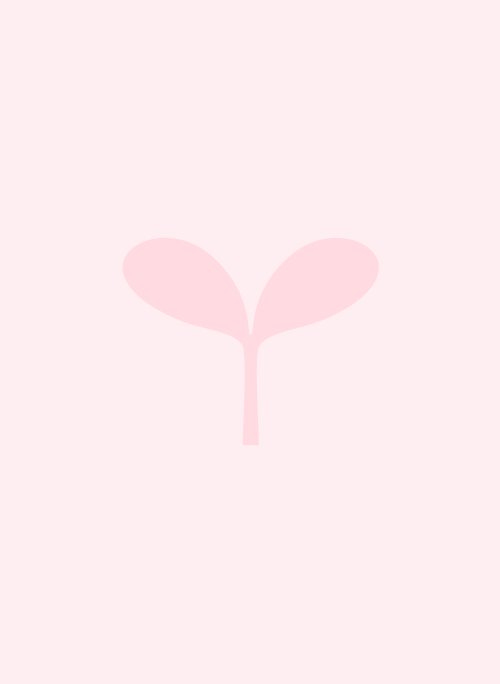少しでも落ち着かせようと、いずみは水月の背を撫でながら青年を見上げた。
真冬の凍りついた湖のような青年の瞳が、スッと細くなる。
「お前が『久遠の花』……若いな。年はいくつだ?」
「……十四になります」
「まだ子供だな。お前のような半人前が、不老不死の秘薬を作れるとは思えんな」
不老不死の秘薬。
その言葉にいずみは息を呑む。
(不老不死が目的――そんな方法なんて、ある訳ないのに……)
あくまでそれは『久遠の花』の伝説に過ぎない。
大昔はそれを信じた者たちに襲われた事はあるが、時代が進み、今はそんな伝説を鵜呑みにする人間はほとんどいなくなっている。
自分でも、他の『久遠の花』でも無理な話。
けれど、無理だと言った瞬間、青年の剣が自分たちを斬り刻む。
水月を生かすために、否定することはできなかった。
「私は物心ついた頃から『久遠の花』のすべてを学びました。……不老不死の術も知っています」
嘘だと分かっていても、言い切るしかない。
いずみが揺らがぬ視線を送り続けていると、青年がおもむろに剣を鞘に収めた。
「もう『久遠の花』はお前しか残っていない。贅沢は言っていられない、か」
青年の呟きに、いずみの目が潤みそうになる。
少なくとも彼らは『久遠の花』を殺す気はない。
だから『久遠の花』は自決したか、『守り葉』の身内や子供を庇おうとして斬られたか。二つに一つしか考えられない。
そうなったのだろうと頭では理解していたが、その事実を聞きたくなかった。
いっそ何も感じられないほど狂ってしまえば、どれだけ楽になれるだろう。
そんなことを思いながら、いずみはふと違和感を覚える。
(どうして私が『久遠の花』の唯一の生き残りだと言い切れるの? この人たちは『久遠の花』の全員の顔を知っていたというの?)
誰かが自分たちのことを彼らに教えていた。そう考えなければ説明がつかない。
でも一体、誰が、何の目的で?
一族の人間が口を割ることはないだろうし、数少ない里へ出入りしていた商人たちも、自分たちがいなければ商売が成り立たない。
お金が欲しいなら、一族を売って莫大な金銭を貰うより、『久遠の花』の薬を豪商や王族に高く売り続けたほうが利益は大きくなる。
もし脅されて渋々彼らに情報を売っていたとしても、商人たちは『守り葉』の毒がどんな物なのか、詳しくは知らされていない。
だから商人たちが犯人なら、彼らが『守り葉』の多様な毒にすべて抗うことなどできないはず。毒が効かないということはあり得ないのだ。
いずみが目まぐるしく頭を働かせていると、いつの間にか追手たちが集まり、周りを取り囲んでいた。
真冬の凍りついた湖のような青年の瞳が、スッと細くなる。
「お前が『久遠の花』……若いな。年はいくつだ?」
「……十四になります」
「まだ子供だな。お前のような半人前が、不老不死の秘薬を作れるとは思えんな」
不老不死の秘薬。
その言葉にいずみは息を呑む。
(不老不死が目的――そんな方法なんて、ある訳ないのに……)
あくまでそれは『久遠の花』の伝説に過ぎない。
大昔はそれを信じた者たちに襲われた事はあるが、時代が進み、今はそんな伝説を鵜呑みにする人間はほとんどいなくなっている。
自分でも、他の『久遠の花』でも無理な話。
けれど、無理だと言った瞬間、青年の剣が自分たちを斬り刻む。
水月を生かすために、否定することはできなかった。
「私は物心ついた頃から『久遠の花』のすべてを学びました。……不老不死の術も知っています」
嘘だと分かっていても、言い切るしかない。
いずみが揺らがぬ視線を送り続けていると、青年がおもむろに剣を鞘に収めた。
「もう『久遠の花』はお前しか残っていない。贅沢は言っていられない、か」
青年の呟きに、いずみの目が潤みそうになる。
少なくとも彼らは『久遠の花』を殺す気はない。
だから『久遠の花』は自決したか、『守り葉』の身内や子供を庇おうとして斬られたか。二つに一つしか考えられない。
そうなったのだろうと頭では理解していたが、その事実を聞きたくなかった。
いっそ何も感じられないほど狂ってしまえば、どれだけ楽になれるだろう。
そんなことを思いながら、いずみはふと違和感を覚える。
(どうして私が『久遠の花』の唯一の生き残りだと言い切れるの? この人たちは『久遠の花』の全員の顔を知っていたというの?)
誰かが自分たちのことを彼らに教えていた。そう考えなければ説明がつかない。
でも一体、誰が、何の目的で?
一族の人間が口を割ることはないだろうし、数少ない里へ出入りしていた商人たちも、自分たちがいなければ商売が成り立たない。
お金が欲しいなら、一族を売って莫大な金銭を貰うより、『久遠の花』の薬を豪商や王族に高く売り続けたほうが利益は大きくなる。
もし脅されて渋々彼らに情報を売っていたとしても、商人たちは『守り葉』の毒がどんな物なのか、詳しくは知らされていない。
だから商人たちが犯人なら、彼らが『守り葉』の多様な毒にすべて抗うことなどできないはず。毒が効かないということはあり得ないのだ。
いずみが目まぐるしく頭を働かせていると、いつの間にか追手たちが集まり、周りを取り囲んでいた。