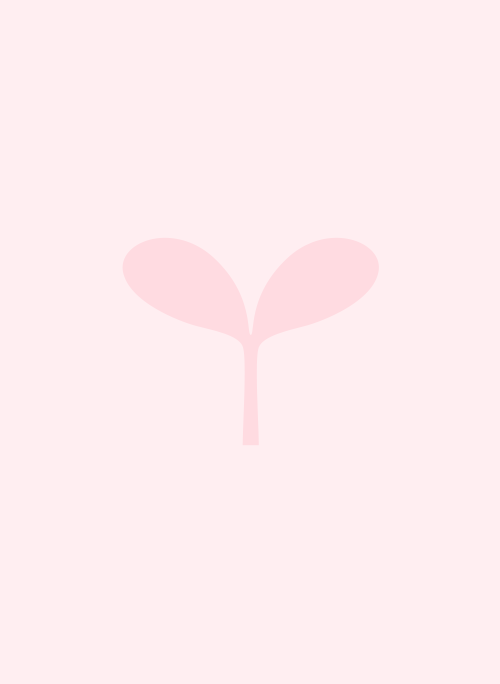水月がキリルの屋敷を出たのは、日が完全に沈みきった頃だった。
まだ雪は降っていないが、夜空から吹きつけられる風は凍てついている。まだ訓練が終わったばかりの熱い体に、寒さが痛いほどしみた。
足を一歩動かす度に全身へ痛みが走り、固く閉じた口から唸る声が漏れ出てくる。
しかしできる限り歩みを早め、水月は城下街の裏通りに入っていった。
ただでさえ国が荒れて人々の心も荒んでいる。ゴロツキも多い。
襲われる危険性もあったが、ここを使ったほうが早く城へ戻ることができる。
自分の帰りを待っているいずみを心配させたくなかった。
民家や店から溢れる明かりは少なく、闇に慣れた目でも先はよく見えない。
体が倒れないよう壁に手をついて支えながら、水月は黙々と歩き続けた。
少し疲れて、フウと息をつく。それでも足を止めることはなかった。
(早く戻らねぇと、いずみに心配かけちまう。こんな痛みなんか大したことはねぇ。アイツの痛みに比べれば……)
きっとここへ来たばかりの頃なら、歩くどころか立ち上がることすらできなかった。
一応キリルの訓練を受けて体が鍛えられているのだと、否が応にも実感する。
水月は忌々しく眉間に皺を寄せて、小さく舌打ちした。
(……感謝はしねぇからな、キリル。テメーが里を襲わなかったら、こんな辛い思いしなくてもよかったんだよ。テメーのせいで――)
心の中でキリルを責めれば責めるほど、水月の胸奥が沈んでいく。
隠れ里を襲撃したキリルたちが悪いのは当然だが、さっさと自分が死んでいれば、この状況を回避できたかもしれない。
すべてをキリルに責任転嫁している自分が、あまりに矮小な弱い人間に思えてならなかった。
疲れきった体と罪悪感で重くなった心を引きずって、どうにか城の前にたどり着く。
ぐるりと迂回して使用人が出入りする裏口へ向かうと、見張りに立っていた兵士がこちらに気づいた。
「こんな遅くまでどこに行ってたんだ……って、何があったんだよナウム? そんなに傷だらけになって」
ヒョロリとした細い体躯の彼は、歳が三つしか違わないということで、知り合ってすぐに親しくなった人間だった。
見知った顔に少し安堵しながら、水月は笑みを浮かべて兵士に近づいた。
「森で薬草を採っていたら、山の斜面で転んじまったんだよ。カッコ悪ぃから、他のヤツらには言うんじゃねーぞ」
兵士は目を丸くしてから小さく吹き出した。
「お前、また転んだのか? ここに来てからしょっちゅう転んでるな。大丈夫なのか?」
キリルに訓練していることを言うなと釘を刺されているので、傷について聞かれたら毎度「転んだんだよ」と言って誤魔化している。
そのせいで、どうも城で顔見知りになった人間からは、しっかりしているのか抜けているのか分からないヤツと思われているようだった。
情けなく見られることに抵抗はあるが、抜け目のある人間のほうが気を許してもらえる。情報を集めるには好都合だった。
水月は肩をすくめて照れ臭そうに笑ってみせた。
「大丈夫、大丈夫。エレーナに薬塗ってもらって休めばすぐに治る」
「妹さんも大変だな、こんな生傷の絶えない兄貴がいて。あんまり心配させるなよ……さ、はやく顔見せに行ってやれよ」
そう言うと兵士は裏口を顎で差し、水月へ行くように促した。
「ああ、ありがとな」
軽く手を振って裏口をくぐると、水月は足早に薬師たちの部屋へと向かう。
足音を立てないようにしつつ、気配を殺し、素早く移動する――キリルから教えられた歩き方。
より多くの経験を積まなければ、キリルを追い越すことはできない。
だから日頃から練習し、この動きが自然にできるよう練習していた。
少しは成果が出てきているようで、下働きの人間とすれ違っても気付かれない頻度は上がっていた。
部屋の扉の前にたどり着いた途端、水月の体から力が抜けそうになる。
今日もどうにか戻ってこられたという安堵感に、思わず口元が緩んだ。
(さあ、少しでも元気そうに見せないとな)
痛みが走る体に「もう少しの辛抱だ」と言い聞かせてから、ゆっくりと扉を開いた。