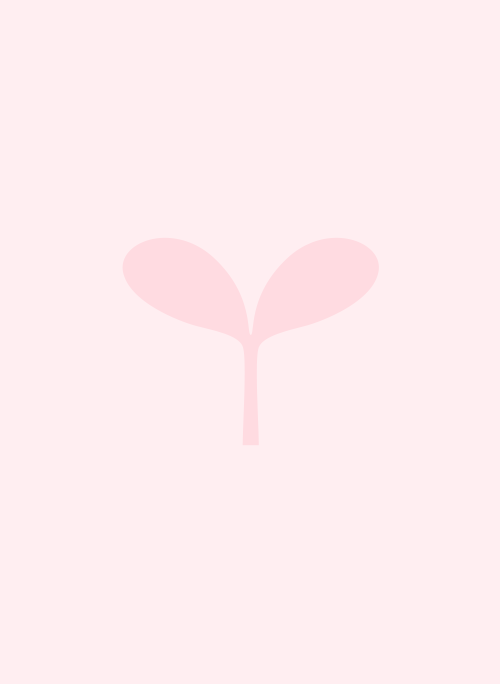ギィ……バタン。
完全に扉が閉じると、瞬く間に静寂が広がり、己の動悸がやけに大きく聞こえる。
胸に手を当てながら安堵の息を吐くと、いずみは緊張で乾いた唇を湿らせた。
(見た目は怖そうだけど、お優しい方で良かったわ。でも……)
おもむろに奥の花壇へ視線を移す。
薬草を植えるために規模が縮小してしまった、観賞用の草花たち。
この温室は王妃のために作られた物だとイヴァンが言っていた。なのに王妃よりも不老不死が優先されているのだから、この現状を知れば悲しむことだろう。
まだ見ぬ王妃のことを思うと、罪悪感で胸が痛くなる。
いずみは眉間に皺を寄せ、ぎゅっと瞼を閉じた。
――と、不意に頭の中で何かがカチリと繋がった。
思わずハッとなり、目を見開いた。
(……あの陛下が、王妃様のために温室を作ったの?)
自分の不老不死ばかりに執着し、気に入らない者は容赦なく斬り捨てる。
噂を聞けばジェラルドが狂王だと誰しも思うだろうし、実際に目の当たりにしてもその考えは変わらない。
そんな狂王が、誰かのために温室を作るということが信じられなかった。
昨日からぼんやりと感じていた違和感が重なり、引っかかっていたことの輪郭が鮮明になった気がした。
(陛下は昔からずっと今のような人柄だったのかしら? ……昔よりも性格や言動が変わってしまう病気もあるわ。それに――)
ゴクリと、息を飲む音が全身に響いた。
(毒を利用して、人為的に狂わされた可能性も考えられるわ)
不意に宰相ペルトーシャの顔が脳裏へ浮かぶ。
ジェラルドから正気を奪い、権力を握って私腹を肥やすために執政する――そう考えて、すぐにいずみは小首を振る。
あくまで一つの可能性であって、実際は違うかもしれない。無闇に人を疑いたくはなかった。
(私、もっと陛下のことを知らなくちゃ……大切なことを見落とさないためにも)
どちらにしても原因が分かれば、より適切な薬を調合することができる。
いずみは大きく頷いて意を決すると、今日の調合に必要な薬草を手早く摘み、温室を後にした。
薬師たちの部屋へ戻り、いずみは辺りを見渡してトトの姿を探す。
各自に1台ずつあてがわれた作業机で、薬師たちが黙々と薬を調合している中、トトの姿は見当たらない。
と、部屋の隅にある休憩用の四角い椅子に腰かけ、首をゆっくり回しているトトが視界に入ってきた。
いずみが近づいていく最中、トトはこちらに気づいて手招き、近くにあった椅子へ座るように目配せした。
こちらから尋ねる前にトトが口を開いた。
「エレーナ、お疲れ様。ちょっと休んでいきなさい」
「ありがとう、おじいちゃん。お言葉に甘えるわ」
いずみはゆっくりと椅子に座って一息つける。
どうやって話を聞き出そうかと考えていると、トトは不思議そうな顔をして首を傾げた。
「いつもと様子が違うね。なにかあったのかい?」
「えっと……あのね、温室にイヴァン様がいらっしゃったの。王妃様を見舞うために、お花を持って行きたいって……それで私が花束を作って差し上げたの」
トトは大げさに目を丸くして見せてから、くしゃりと笑った。
「イヴァン様は優しい御方だからね。顔は強面でも、怖くはなかったんじゃないかね?」
「ええ、とても気さくな方だったわ。その時に温室のことを少し教えて頂いたの。陛下が王妃様のために作らせた物だって……」
いずみが言葉を詰まらせて困惑の色を滲ませると、トトはその思いを汲み取って小刻みに頷く。
どこか悲しそうな、けれど優しい眼差しと微笑みを浮かべながら。
「陛下が王となられてからすぐに、王妃様を迎えることになったんだよ。王妃様は他国のお方。さぞ慣れぬ地で心細かろうと陛下は慮られて、少しでも王妃様のお心を癒すことができればと温室を作られたんだ」
今のジェラルドからは想像できない話。
イヴァンから聞いた時は半信半疑だったが、トトも同じことを言うなら真実なのだろう。
もっと他の話を聞きたいところだが、怪しまれる言動は慎まなければいけない。
怪しまれないよう、いずみがどう話を持っていこうかと考えていると、トトが思い出をさらに語ってくれた。
「懐かしいね……私は陛下がお生まれになった頃から知っているけれど、昔はイヴァン様以上に快活で気さくな方だったんだ。王位に就く前は積極的に城の外へ出て、民の生活を見たり、民の声を聞いたりしていたんだよ。本当にお優しい方だった……」
完全に扉が閉じると、瞬く間に静寂が広がり、己の動悸がやけに大きく聞こえる。
胸に手を当てながら安堵の息を吐くと、いずみは緊張で乾いた唇を湿らせた。
(見た目は怖そうだけど、お優しい方で良かったわ。でも……)
おもむろに奥の花壇へ視線を移す。
薬草を植えるために規模が縮小してしまった、観賞用の草花たち。
この温室は王妃のために作られた物だとイヴァンが言っていた。なのに王妃よりも不老不死が優先されているのだから、この現状を知れば悲しむことだろう。
まだ見ぬ王妃のことを思うと、罪悪感で胸が痛くなる。
いずみは眉間に皺を寄せ、ぎゅっと瞼を閉じた。
――と、不意に頭の中で何かがカチリと繋がった。
思わずハッとなり、目を見開いた。
(……あの陛下が、王妃様のために温室を作ったの?)
自分の不老不死ばかりに執着し、気に入らない者は容赦なく斬り捨てる。
噂を聞けばジェラルドが狂王だと誰しも思うだろうし、実際に目の当たりにしてもその考えは変わらない。
そんな狂王が、誰かのために温室を作るということが信じられなかった。
昨日からぼんやりと感じていた違和感が重なり、引っかかっていたことの輪郭が鮮明になった気がした。
(陛下は昔からずっと今のような人柄だったのかしら? ……昔よりも性格や言動が変わってしまう病気もあるわ。それに――)
ゴクリと、息を飲む音が全身に響いた。
(毒を利用して、人為的に狂わされた可能性も考えられるわ)
不意に宰相ペルトーシャの顔が脳裏へ浮かぶ。
ジェラルドから正気を奪い、権力を握って私腹を肥やすために執政する――そう考えて、すぐにいずみは小首を振る。
あくまで一つの可能性であって、実際は違うかもしれない。無闇に人を疑いたくはなかった。
(私、もっと陛下のことを知らなくちゃ……大切なことを見落とさないためにも)
どちらにしても原因が分かれば、より適切な薬を調合することができる。
いずみは大きく頷いて意を決すると、今日の調合に必要な薬草を手早く摘み、温室を後にした。
薬師たちの部屋へ戻り、いずみは辺りを見渡してトトの姿を探す。
各自に1台ずつあてがわれた作業机で、薬師たちが黙々と薬を調合している中、トトの姿は見当たらない。
と、部屋の隅にある休憩用の四角い椅子に腰かけ、首をゆっくり回しているトトが視界に入ってきた。
いずみが近づいていく最中、トトはこちらに気づいて手招き、近くにあった椅子へ座るように目配せした。
こちらから尋ねる前にトトが口を開いた。
「エレーナ、お疲れ様。ちょっと休んでいきなさい」
「ありがとう、おじいちゃん。お言葉に甘えるわ」
いずみはゆっくりと椅子に座って一息つける。
どうやって話を聞き出そうかと考えていると、トトは不思議そうな顔をして首を傾げた。
「いつもと様子が違うね。なにかあったのかい?」
「えっと……あのね、温室にイヴァン様がいらっしゃったの。王妃様を見舞うために、お花を持って行きたいって……それで私が花束を作って差し上げたの」
トトは大げさに目を丸くして見せてから、くしゃりと笑った。
「イヴァン様は優しい御方だからね。顔は強面でも、怖くはなかったんじゃないかね?」
「ええ、とても気さくな方だったわ。その時に温室のことを少し教えて頂いたの。陛下が王妃様のために作らせた物だって……」
いずみが言葉を詰まらせて困惑の色を滲ませると、トトはその思いを汲み取って小刻みに頷く。
どこか悲しそうな、けれど優しい眼差しと微笑みを浮かべながら。
「陛下が王となられてからすぐに、王妃様を迎えることになったんだよ。王妃様は他国のお方。さぞ慣れぬ地で心細かろうと陛下は慮られて、少しでも王妃様のお心を癒すことができればと温室を作られたんだ」
今のジェラルドからは想像できない話。
イヴァンから聞いた時は半信半疑だったが、トトも同じことを言うなら真実なのだろう。
もっと他の話を聞きたいところだが、怪しまれる言動は慎まなければいけない。
怪しまれないよう、いずみがどう話を持っていこうかと考えていると、トトが思い出をさらに語ってくれた。
「懐かしいね……私は陛下がお生まれになった頃から知っているけれど、昔はイヴァン様以上に快活で気さくな方だったんだ。王位に就く前は積極的に城の外へ出て、民の生活を見たり、民の声を聞いたりしていたんだよ。本当にお優しい方だった……」