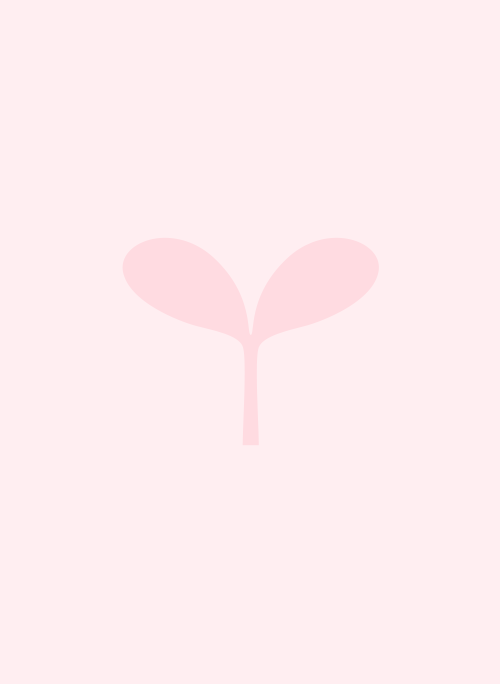◇◇◇◇◇◇◇◇◇
翌日。いずみは朝食を終えてから、日課となっている薬草たちを手入れするため、温室へと向かった。
外の花壇にあるのは寒さに丈夫な物や、滅多に枯れない生命力の強い薬草が植えられている。
こちらはたまに雑草を取るぐらいで充分だが、温室で育てている物は、とても繊細で手のかかる薬草ばかり。自然と温室にいる時間は長くなっていた。
剪定バサミを手にしながら、いずみはしゃがんで低木に顔を近づけると、細い枝を見つけては切り落としていく。
だが、不意に昨日の疑問を思い出してしまい、動かしていた手を止める。
(考えても仕方のないことなのに、どうして気になるのかしら?)
はっきり何がと断言することはできないが、違和感を覚えてしまうのだ。
もしかすると、見過ごせない何かがあるのかもしれない。
父に薬師の知識を叩き込まれていた時、言われたことがある。
人を癒すということは、人の命を扱うということ。
ちょっとした変化を気のせいだと済ませてしまったせいで、命を落とすこともあるのだ。
命が消えれば取り返しがつかなくなる。どれだけ慎重になっても、やり過ぎることはないのだ、と。
もう会えない父の顔が頭に浮かび、いずみの目に涙が滲んだ。
(父さん、母さん、みなも――)
感情が走り出してしまい、冷静に考えられなくなる。
どうにか気持ちを落ち着けようと、硬く目を閉じながら息を深く吸った。
その刹那、キィッと素早く扉が開く音がした。
この時間に温室へ来たことがあるのは、今のところ水月ぐらいだ。
ハッとなっていずみは指で涙を拭い、慌てて笑顔を作って振り向く。
入って来たのは、黒い軍服をまとった青年だった
首筋まで伸びた波打つ赤金の髪、鋭い目付きに不敵さが宿る群青の瞳。大きく力強そうな鷲鼻が、彼の印象を猛々しくしていた。
彼も人がいて驚いているのか、目を見開き、こちらを凝視していた。
何か言わなければと思うのに、漂ってくる威圧感に気圧され、いずみは固まったまま青年を見続ける。
と、青年はバツが悪そうに顔をしかめ、頭を掻いた。
「悪いな、急に入って来て。別に取って食べる気はないから、そんなに怯えないでくれ」
返事をしようとしたが口は開こうとせず、いずみは大きく頷いてみせる。
青年は薄っすらと苦笑を浮かべてから、扉を閉めてこちらへ歩いて来た。
「見ない顔だが、お前は何者だ? 一体何をしている?」
「は、はい、私は薬師トトの孫娘エレーナ……祖父の手伝いで、こちらに生えている薬草の手入れをしております」
やっと出した声は裏返っており、いずみの顔が恥ずかしさで熱くなる。
青年は「ほう」と声を漏らすと、まじまじとこちらを見つめてきた。
「トトの孫娘か、初耳だな。つい最近ここへ来たばかりか?」
いずみが「そうです」と答えると、心なしか青年の顔に悪戯めいた笑みが浮かんだ。
「その様子からすると、俺が誰か分からないようだな」
「はい……あの、失礼ですがお名前を教えて頂けませんか?」
「俺の名はイヴァン……顔は分からずとも、名前ぐらいは知っているだろ?」
イヴァン。確かに聞き覚えのある名前だ。
けれど、それ以上は思い出せず、いずみはつい小首を傾げる。
唐突にイヴァンは声を上げて笑った。
「ハハ……この国で俺を知らない人間がいるとはな。まあいい、それも一興だ」
立派な身なりをしているのだから、きっと立場がある人なのだろう。
そんなことを漠然と考えた後、いずみはハッとなった。
「も、申し訳ありませんイヴァン様。私――」
慌てて跪こうとしていずみを、イヴァンは首を横に振って静止した。
「堅苦しいのは苦手なんだ、そんなに畏まらないでくれ」
否定しないところを見ると、立場があるのは間違いないようだ。しかし、それを誇示しない人柄に、いずみは強ばっていた肩から力が抜けた。
「分かりました、イヴァン様。ありがとうございます」
トトやイヴァンのように優しさを感じられる人に出会えると、心から嬉しく思える。
自然と顔の力みが取れて、いつの間にかいずみは微笑んでいた。
翌日。いずみは朝食を終えてから、日課となっている薬草たちを手入れするため、温室へと向かった。
外の花壇にあるのは寒さに丈夫な物や、滅多に枯れない生命力の強い薬草が植えられている。
こちらはたまに雑草を取るぐらいで充分だが、温室で育てている物は、とても繊細で手のかかる薬草ばかり。自然と温室にいる時間は長くなっていた。
剪定バサミを手にしながら、いずみはしゃがんで低木に顔を近づけると、細い枝を見つけては切り落としていく。
だが、不意に昨日の疑問を思い出してしまい、動かしていた手を止める。
(考えても仕方のないことなのに、どうして気になるのかしら?)
はっきり何がと断言することはできないが、違和感を覚えてしまうのだ。
もしかすると、見過ごせない何かがあるのかもしれない。
父に薬師の知識を叩き込まれていた時、言われたことがある。
人を癒すということは、人の命を扱うということ。
ちょっとした変化を気のせいだと済ませてしまったせいで、命を落とすこともあるのだ。
命が消えれば取り返しがつかなくなる。どれだけ慎重になっても、やり過ぎることはないのだ、と。
もう会えない父の顔が頭に浮かび、いずみの目に涙が滲んだ。
(父さん、母さん、みなも――)
感情が走り出してしまい、冷静に考えられなくなる。
どうにか気持ちを落ち着けようと、硬く目を閉じながら息を深く吸った。
その刹那、キィッと素早く扉が開く音がした。
この時間に温室へ来たことがあるのは、今のところ水月ぐらいだ。
ハッとなっていずみは指で涙を拭い、慌てて笑顔を作って振り向く。
入って来たのは、黒い軍服をまとった青年だった
首筋まで伸びた波打つ赤金の髪、鋭い目付きに不敵さが宿る群青の瞳。大きく力強そうな鷲鼻が、彼の印象を猛々しくしていた。
彼も人がいて驚いているのか、目を見開き、こちらを凝視していた。
何か言わなければと思うのに、漂ってくる威圧感に気圧され、いずみは固まったまま青年を見続ける。
と、青年はバツが悪そうに顔をしかめ、頭を掻いた。
「悪いな、急に入って来て。別に取って食べる気はないから、そんなに怯えないでくれ」
返事をしようとしたが口は開こうとせず、いずみは大きく頷いてみせる。
青年は薄っすらと苦笑を浮かべてから、扉を閉めてこちらへ歩いて来た。
「見ない顔だが、お前は何者だ? 一体何をしている?」
「は、はい、私は薬師トトの孫娘エレーナ……祖父の手伝いで、こちらに生えている薬草の手入れをしております」
やっと出した声は裏返っており、いずみの顔が恥ずかしさで熱くなる。
青年は「ほう」と声を漏らすと、まじまじとこちらを見つめてきた。
「トトの孫娘か、初耳だな。つい最近ここへ来たばかりか?」
いずみが「そうです」と答えると、心なしか青年の顔に悪戯めいた笑みが浮かんだ。
「その様子からすると、俺が誰か分からないようだな」
「はい……あの、失礼ですがお名前を教えて頂けませんか?」
「俺の名はイヴァン……顔は分からずとも、名前ぐらいは知っているだろ?」
イヴァン。確かに聞き覚えのある名前だ。
けれど、それ以上は思い出せず、いずみはつい小首を傾げる。
唐突にイヴァンは声を上げて笑った。
「ハハ……この国で俺を知らない人間がいるとはな。まあいい、それも一興だ」
立派な身なりをしているのだから、きっと立場がある人なのだろう。
そんなことを漠然と考えた後、いずみはハッとなった。
「も、申し訳ありませんイヴァン様。私――」
慌てて跪こうとしていずみを、イヴァンは首を横に振って静止した。
「堅苦しいのは苦手なんだ、そんなに畏まらないでくれ」
否定しないところを見ると、立場があるのは間違いないようだ。しかし、それを誇示しない人柄に、いずみは強ばっていた肩から力が抜けた。
「分かりました、イヴァン様。ありがとうございます」
トトやイヴァンのように優しさを感じられる人に出会えると、心から嬉しく思える。
自然と顔の力みが取れて、いつの間にかいずみは微笑んでいた。