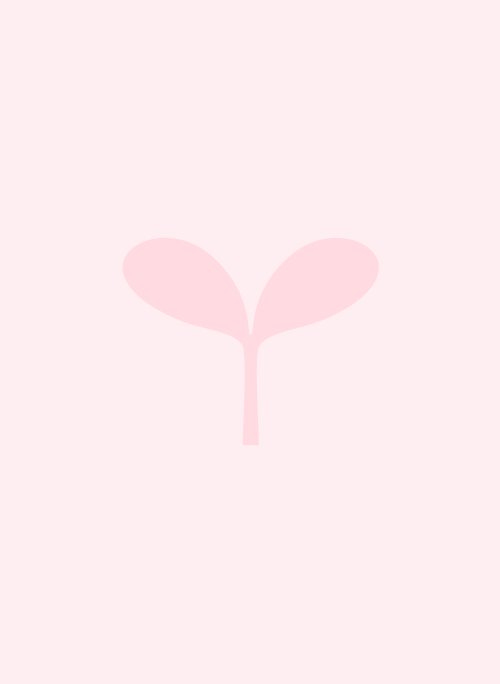「何だよそれ。あの王様なら、速攻で斬り捨ててもおかしくないのに……本当に訳が分からねぇな」
夜、二人にあてがわれた部屋で夕方のことを伝えると、水月は大きなため息をつきながら、腕を組んで唸った。
寝台に腰かけたまま、いずみは足元の床に座っている水月へ小さく頷いてみせる。
「もしかして陛下は、宰相閣下のことをすごく大切に思っているのかしら? 執政をすべてお任せしているくらいだし――」
「どうなんだろうな……自分の懐を潤すばっかりで、まともな政をしていないって評判だぜ? 城の人間から聞いた話だと、重要な役職であっても少し失敗しただけで容赦しないらしいのに」
水月は身を前に乗り出し、いずみに顔を近づけて声を潜める。
「他のお偉いさんはコロコロ変わるのに、あの宰相様だけは二十年以上も今の地位に居続けているって話だ。オレら庶民と考えが違うってこともあると思うが、すごく胡散臭いよな」
「私もそう思うわ。それに――」
不意にいずみの脳裏へ、初めて見たジェラルドの微笑が浮かぶ。
いつも気だるそうにして精気はあまり感じられないが、それでも王の威厳は健在だ。もし体が完全に回復すれば、どんな人でもひれ伏さずにはいられないだろう。
そんな王の威厳が、あの一瞬だけ消えていた。
(もしかして、何か弱みを握られていたり、脅されていたりするのかしら? でも、陛下がそんなことに屈してしまうとは思えないし……)
口元に手を当てて考えていると、水月の手がいずみの頭をくしゃりと撫でた。
「理由が分かったところで、オレらじゃ何もできねぇよ。余計なことには首を突っ込まないほうがいいぜ」
確かに自分たちのような地位もない余所者の人間が、どうこうできるようなものではない。
少しでも怪しい動きをすれば容赦はしない、とキリルからも言われている。水月と生き残るためには、危ない橋を渡る訳にはいかなかった。
「……そうよね。これ以上は考えないようにするわ」
こちらの返答を聞くと、水月はポンといずみの頭を軽く叩いてから手を離し、そのまま後ろに手をついた。
「ところで、陛下の治療の具合はどうなんだ? 少しは良くなっているのか?」
「ええ、本当に少しだけ。個人差もあるし、長年体調を崩されて体の抵抗力も落ちているから、仕方ないとは思うけれど……」
いずみが言葉を詰まらせていると――。
――突然水月の背後から、「そうか」というキリルの声がした。
思わずいずみの肩は跳ね上がり、水月の目はぎょっと丸くなる。
二人して弾かれたように振り向くと、いつの間にかキリルが腕を組んで立っていた。
「い、いつもいつも気配消して現れんな! テメーは人を驚かすことが趣味なのかよ」
「別に趣味ではない。単なる習慣だ」
水月の文句をさらりと流し、キリルはいずみを見据える。
「今までは城の薬師たちの薬を飲んでも、現状を維持することしかできなかった。それに比べれば、確かに改善はしている」
素人目に見るだけでは、ジェラルドの容態は変わっていないように見えるはず。
聞いてもいいものだろうかと一瞬迷ってから、いずみはキリルに尋ねてみた。
「あの、どうして改善していると分かるのですか? 見た目には分からないと思うのですけれど……」
「外観は変わられていないが、陛下の精気がわずかに強くなられているのは肌で感じ取れた。良い傾向だ」
言っていることがよく分からず、いずみは首を傾げる。と、それを見て水月は苦笑を浮かべて肩をすくめた。
「コイツら、視界の悪い所で戦ったりする時のために、人の気配を汲み取る訓練をしているんだよ。扉一枚隔てた向こう側の人の動きも分かるらしい。だから相手が弱っているかどうかを見極めるのは楽勝なんだろ?」
水月の言葉にキリルが無言で小さく頷く。当然だと言わんばかりの態度から、彼の自信が伺える。
本当にこの人は自分と同じ人間なのだろうかといずみが考えていると、キリルは「ところで」と話を切り替えた。
「娘、明日の夕方までに強い痛み止めの薬を用意しておけ」
「分かりました。調合が終わったらすぐにお渡しします――」
いずみが言い終わらな内に、キリルが首を横に振った。
「いや、お前が持っていればいい。使うのは俺ではないからな」
そう言うと、キリルはすうっと視線を水月に移す。
一瞬間が開いてから、水月が「ゲッ」という声を上げ、体をすくめてキリルから距離を取った。
「さらにオレをいたぶる気かよ! 本っっ当に容赦ねぇな。まさかアンタも人をいたぶって楽しむ類の人間か?」
「違う。今までは素人ということで手加減していたが、少しは慣れてきたようだからな。明日から本気を出していく」