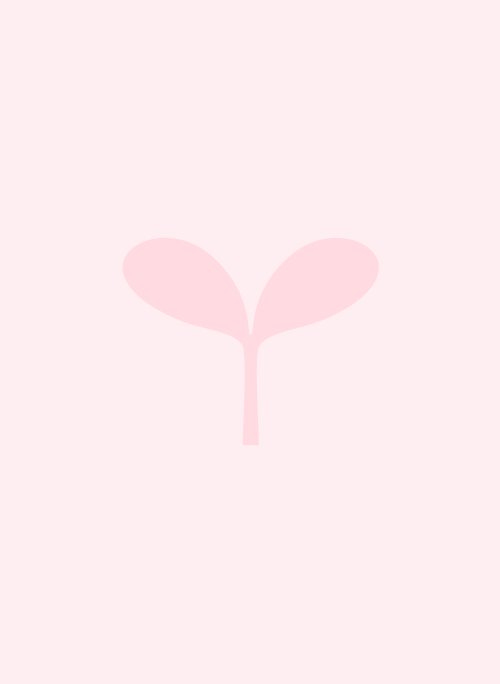王の許しを得てキリルは「分かりました」と頷くと、無音で踵を返して扉のほうへと歩いて行く。
一呼吸おいて、トトがやおらと立ち上がった。
「では私たちはこれで失礼させて頂きま――」
「良い、ここにいろ。話はすぐに終わる……あやつの話よりも、余の不老不死のほうが重要だ。余の体を片手間に診られては困る」
今日は機嫌がいいのか、珍しくジェラルドが微笑を浮かべる。
どこか諦めたような、寂しげな笑み。
初めて人らしい感情が見えた気がして、いずみは一瞬我を忘れてジェラルドをまじまじと見つめた。
「エレーナ、一旦こちらへ下がりなさい」
トトに呼びかけられて、いずみは慌てて箱を持って立ち上がり、ジェラルドに一礼してからトトの隣へ並ぶ。
少し息が乱れたいずみの背中をトトは軽く叩き、小声で「落ち着きなさい」と気遣ってくれた。
いずみは目配せをして、小さく頷いてみせる。水月が近くにいない今、トトの支えが本当にありがたかった。
間もなくして扉が開き、恰幅の良い中年の男がこちらへ近づいて来る。
エラが張った四角くごつい顔に、くるくるとよく動きそうな丸くて大きな目。金色のヒゲは鼻の下で、きれいに分かれて左右に跳ねている。ゆったりとした服で誤魔化しているのだろうが、お腹の膨らみは隠しきれていなかった。
「お目通りの許可を頂き、ありがとうございます陛下」
男はわざとらしく声を弾ませ、口端を上げてにこやかな表情を浮かべてジェラルドを仰ぐ。
億劫そうに目を細め、ジェラルドは男と目を合わせた。
「一体何の用だペルトーシャ? 政務のことはお前にすべて任せている。余に確認せずとも、お前の好きなようにしてくれ」
「陛下のご信頼を承り、大変光栄に存じます。ただ……今日は陛下のお体を心配しまして、こちらへ参った次第でございます」
ペルトーシャはちらりとこちらを見やってから、心配げな声で言葉を続ける。
「最近トトが毎日のように陛下の元を訪れていると聞きまして、どこかお具合が悪いのかと……王妃様だけでなく陛下もお倒れになっては、このペルトーシャ、胸が張り裂けてしまいます」
「別に余の体に変わりはない、いつも通りだ。なあ、トトよ」
ジェラルドに話を振られて、トトは「はい」と頷いた。
「閣下、ご安心下さい。つい先月、陛下のお望みを叶えられるかもしれない薬草を入手しましたので、陛下に飲んで頂いているのです。今まで扱ったことのない未知の物ゆえ、陛下のお体に合うのか分かりませぬので、こうして私が薬を運びながらお体を診ております」
トトの話を聞き終えると、ペルトーシャは見た目にも分かるくらいに肩を脱力させ、ふうっ、と大きなため息を吐き出す。
本当に心配しているのかもしれないが、どこか演技めいているように見えた。
「何事もなくてよろしゅうございました。一日でも早く陛下のお望みが叶うよう、私も全力を尽くしていきます。政は私がしっかとこなしていきますから、陛下は心置きなく不老不死の道を歩まれて下さい」
嬉々として発言するペルトーシャに、いずみは心の中で眉をひそめる。
城を出る機会がある水月から、城下街であっても退廃が進んでおり、人々の貧困も酷いと聞いている。
城下街で暴漢が出れば容赦なく見回りの兵に斬り捨てられるため、最低限の治安は維持できているが、他の村や町は酷い荒れ様らしい。
執政のことはよく知らないが、悪政が続いているのだということは分かる。
分かっているのに何もできない自分が歯がゆくて、胸が苦しくなった。
と、ペルトーシャがトトから視線をずらし、物言いたげにいずみを見つめてきた。
その様子にすぐ気づいたトトは、いずみを見やってから口を開いた。
「彼女は私の孫で、エレーナと申します。私の助手として同伴することを陛下にお許し頂きました」
トトの話に合わせていずみが会釈すると、ペルトーシャは「そうか、そうか」と一人頷き、こちらへ笑いかけてくる。
「陛下に失礼のないよう心がけながら、しっかりとトトを手伝うのだぞ」
「は、はい、ペルトーシャ様……」
緊張して上ずった声を出しつつ、いずみはもう一度会釈する。
頭を上げた時には、もうペルトーシャは視線をジェラルドへ移し、話を再開させていた。
丁寧ながら回りくどい言い回しで、ペルトーシャは他愛のない話を紡いでいく。
傍から聞いていると、中身はなく、聞き続けるのが苦痛になってくる。
けれどジェラルドは気だるそうに応対するだけで、怒りを露わにすることはなかった。
一呼吸おいて、トトがやおらと立ち上がった。
「では私たちはこれで失礼させて頂きま――」
「良い、ここにいろ。話はすぐに終わる……あやつの話よりも、余の不老不死のほうが重要だ。余の体を片手間に診られては困る」
今日は機嫌がいいのか、珍しくジェラルドが微笑を浮かべる。
どこか諦めたような、寂しげな笑み。
初めて人らしい感情が見えた気がして、いずみは一瞬我を忘れてジェラルドをまじまじと見つめた。
「エレーナ、一旦こちらへ下がりなさい」
トトに呼びかけられて、いずみは慌てて箱を持って立ち上がり、ジェラルドに一礼してからトトの隣へ並ぶ。
少し息が乱れたいずみの背中をトトは軽く叩き、小声で「落ち着きなさい」と気遣ってくれた。
いずみは目配せをして、小さく頷いてみせる。水月が近くにいない今、トトの支えが本当にありがたかった。
間もなくして扉が開き、恰幅の良い中年の男がこちらへ近づいて来る。
エラが張った四角くごつい顔に、くるくるとよく動きそうな丸くて大きな目。金色のヒゲは鼻の下で、きれいに分かれて左右に跳ねている。ゆったりとした服で誤魔化しているのだろうが、お腹の膨らみは隠しきれていなかった。
「お目通りの許可を頂き、ありがとうございます陛下」
男はわざとらしく声を弾ませ、口端を上げてにこやかな表情を浮かべてジェラルドを仰ぐ。
億劫そうに目を細め、ジェラルドは男と目を合わせた。
「一体何の用だペルトーシャ? 政務のことはお前にすべて任せている。余に確認せずとも、お前の好きなようにしてくれ」
「陛下のご信頼を承り、大変光栄に存じます。ただ……今日は陛下のお体を心配しまして、こちらへ参った次第でございます」
ペルトーシャはちらりとこちらを見やってから、心配げな声で言葉を続ける。
「最近トトが毎日のように陛下の元を訪れていると聞きまして、どこかお具合が悪いのかと……王妃様だけでなく陛下もお倒れになっては、このペルトーシャ、胸が張り裂けてしまいます」
「別に余の体に変わりはない、いつも通りだ。なあ、トトよ」
ジェラルドに話を振られて、トトは「はい」と頷いた。
「閣下、ご安心下さい。つい先月、陛下のお望みを叶えられるかもしれない薬草を入手しましたので、陛下に飲んで頂いているのです。今まで扱ったことのない未知の物ゆえ、陛下のお体に合うのか分かりませぬので、こうして私が薬を運びながらお体を診ております」
トトの話を聞き終えると、ペルトーシャは見た目にも分かるくらいに肩を脱力させ、ふうっ、と大きなため息を吐き出す。
本当に心配しているのかもしれないが、どこか演技めいているように見えた。
「何事もなくてよろしゅうございました。一日でも早く陛下のお望みが叶うよう、私も全力を尽くしていきます。政は私がしっかとこなしていきますから、陛下は心置きなく不老不死の道を歩まれて下さい」
嬉々として発言するペルトーシャに、いずみは心の中で眉をひそめる。
城を出る機会がある水月から、城下街であっても退廃が進んでおり、人々の貧困も酷いと聞いている。
城下街で暴漢が出れば容赦なく見回りの兵に斬り捨てられるため、最低限の治安は維持できているが、他の村や町は酷い荒れ様らしい。
執政のことはよく知らないが、悪政が続いているのだということは分かる。
分かっているのに何もできない自分が歯がゆくて、胸が苦しくなった。
と、ペルトーシャがトトから視線をずらし、物言いたげにいずみを見つめてきた。
その様子にすぐ気づいたトトは、いずみを見やってから口を開いた。
「彼女は私の孫で、エレーナと申します。私の助手として同伴することを陛下にお許し頂きました」
トトの話に合わせていずみが会釈すると、ペルトーシャは「そうか、そうか」と一人頷き、こちらへ笑いかけてくる。
「陛下に失礼のないよう心がけながら、しっかりとトトを手伝うのだぞ」
「は、はい、ペルトーシャ様……」
緊張して上ずった声を出しつつ、いずみはもう一度会釈する。
頭を上げた時には、もうペルトーシャは視線をジェラルドへ移し、話を再開させていた。
丁寧ながら回りくどい言い回しで、ペルトーシャは他愛のない話を紡いでいく。
傍から聞いていると、中身はなく、聞き続けるのが苦痛になってくる。
けれどジェラルドは気だるそうに応対するだけで、怒りを露わにすることはなかった。