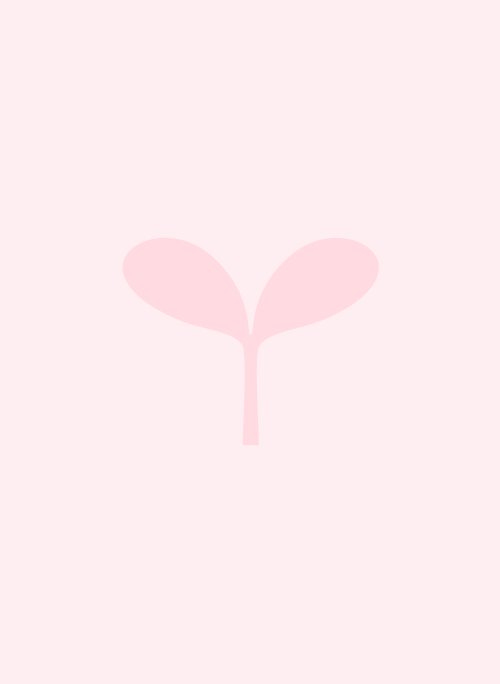表情を変えないまま、キリルは大したことではないと言わんばかりの、淡々とした口調で言葉を続けた。
「――陛下のご命令は、『久遠の花』を生け捕りにすること。命を奪えとは言われていない。……お前たちが抵抗しなければ、誰も死なずに済んだ」
「そんなことは……」
反論しかけて、いずみは言葉を失う。
キリルの言う通り、抵抗しなければみんな死ぬことはなかったのかもしれない。
でも、もしそうだとすれば、一族を守って死んだことも、秘密を守って命を断ったことも、意味はなかったということになる。
一族の犠牲が無駄だったなんて、認めたくない。
再び潤みそうになるのを堪えていると――。
――そっといずみの肩に、水月の手が載せられた。
「誰も死なずに済んだ、だって? ……ふざけんなよ。どうせ何人か確保できれば、残りはさっさと殺して、復讐の芽を全部摘む気だったんだろうが」
怒りからなのか、怯えからなのか、水月の手が細かく震えている。
それを抑えるように、水月の手に力が加わり、いずみの肩に軽く痛みが走った。
「それに、ジェラルド王の噂は聞いている。……逆らう者はもちろん、機嫌が悪いってだけで目の前の相手を斬り殺す、狂った王だってな。そんな人間が、不老不死を叶えた後、用が無くなった人間を生かすとは思えねぇ」
感情を感じさせなかったキリルの目に、鋭い光が宿る。
刹那、キリルの腕が伸び、水月の顎を掴んだ。
「……口には気をつけろ。これ以上陛下を侮辱すれば、貴様の顎を砕く」
淡々とした調子はそのままに、キリルの声が低くなる。
容赦なく指が顔に食い込まれ、水月から呻き声が聞こえてきた。
この人は本気でそうするつもりだ。
咄嗟にいずみはキリルの袖を掴み、間近になった彼の顔を見上げた。
「止めて下さい! 陛下のお望みが一刻でも早く叶うよう、精一杯頑張りますから!」
いずみの目を、キリルが無言で見つめてくる。
こちらの心を全て読もうとしているように思えて、いずみの体が強張った。
しばらくしてキリルは腕の力を抜き、水月から手を離した。
「その言葉、忘れるなよ。少しでも妙な真似をすれば、そこの小僧を死ぬより辛い目に合わせるからな」
そう言うと、キリルは音もなく立ち上がり、いずみと水月を見下ろした。
「――陛下のご命令は、『久遠の花』を生け捕りにすること。命を奪えとは言われていない。……お前たちが抵抗しなければ、誰も死なずに済んだ」
「そんなことは……」
反論しかけて、いずみは言葉を失う。
キリルの言う通り、抵抗しなければみんな死ぬことはなかったのかもしれない。
でも、もしそうだとすれば、一族を守って死んだことも、秘密を守って命を断ったことも、意味はなかったということになる。
一族の犠牲が無駄だったなんて、認めたくない。
再び潤みそうになるのを堪えていると――。
――そっといずみの肩に、水月の手が載せられた。
「誰も死なずに済んだ、だって? ……ふざけんなよ。どうせ何人か確保できれば、残りはさっさと殺して、復讐の芽を全部摘む気だったんだろうが」
怒りからなのか、怯えからなのか、水月の手が細かく震えている。
それを抑えるように、水月の手に力が加わり、いずみの肩に軽く痛みが走った。
「それに、ジェラルド王の噂は聞いている。……逆らう者はもちろん、機嫌が悪いってだけで目の前の相手を斬り殺す、狂った王だってな。そんな人間が、不老不死を叶えた後、用が無くなった人間を生かすとは思えねぇ」
感情を感じさせなかったキリルの目に、鋭い光が宿る。
刹那、キリルの腕が伸び、水月の顎を掴んだ。
「……口には気をつけろ。これ以上陛下を侮辱すれば、貴様の顎を砕く」
淡々とした調子はそのままに、キリルの声が低くなる。
容赦なく指が顔に食い込まれ、水月から呻き声が聞こえてきた。
この人は本気でそうするつもりだ。
咄嗟にいずみはキリルの袖を掴み、間近になった彼の顔を見上げた。
「止めて下さい! 陛下のお望みが一刻でも早く叶うよう、精一杯頑張りますから!」
いずみの目を、キリルが無言で見つめてくる。
こちらの心を全て読もうとしているように思えて、いずみの体が強張った。
しばらくしてキリルは腕の力を抜き、水月から手を離した。
「その言葉、忘れるなよ。少しでも妙な真似をすれば、そこの小僧を死ぬより辛い目に合わせるからな」
そう言うと、キリルは音もなく立ち上がり、いずみと水月を見下ろした。