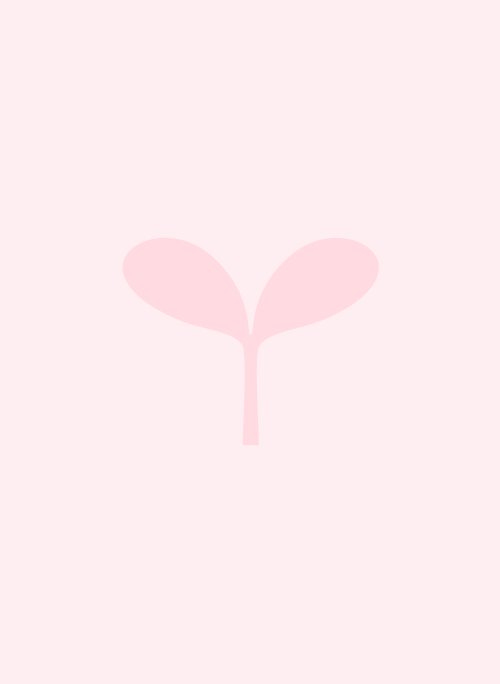しばらくして涙が底を尽き、いずみの嗚咽が治まっていく。と――。
「気は済んだか、娘。話せるならこっちを向け」
突然、背後から抑揚のない声が聞こえてくる。
弾かれたようにいずみが振り向くと、いつの間にか水月を斬ろうとしていた青年が、木箱に腰をかけてこちらを見ていた。
まったく気配を感じなかった……。
得体の知れない不気味さを感じつつ、いずみは座り直して青年と向き合う。
無機質な目が、こちらを品定めするように見つめてくる。
そしておもむろに、青年は小さく息をついて腕組みをした。
「女子供は騒々しいだけだと思っていたが、お前は違うようだな。その利発さなら、我が主の期待に応えてくれそうだ」
我が主とは誰なのだろう?
聞き返そうとして、いずみは思いとどまる。闇雲に話を聞いても混乱するだけだ。
まずは順を追って話を聞こう。
いずみは乾いた唇を湿らせ、口を開いた。
「あの、貴方がたは一体何者なのですか?」
青年は目を細め、わずかに思案してから言葉を紡いだ。
「俺の名はキリル……俺たちはバルディグの偉大なる王、ジェラルド陛下に仕えている者だ」
バルディグ――大陸の北部にある国で、北方で最も厳しい冬を迎えていると噂に聞いたことがある。
あと覚えているのは、大人たちが「バルディグにはなるべく行きたくないな」と口を揃えて言っていたこと。
話を聞いた時に、理由は聞かなかった。きっと酷い寒さで行き来するのが大変なのだろう、としか考えていなかった。
いずみは唾を呑み込むと、キリルへ向ける眼差しを強くした。
「国王陛下が不老不死を望まれたから、『久遠の花』を捕らえにきたのですか?」
「ああ、その通りだ。陛下は数年ほど前から、死ぬことを非常に恐れていらっしゃる。だから『久遠の花』の伝承を聞き、何が何でも連れて来いと命じられたのだ」
キリルの話を聞きながら、いずみは手を強く握り込み、感情のおもむくままに言いたくなる気持ちを抑え込む。
「どうして力づくで私たちを捕らえようとしたのですか? どなたか隠れ里に来て『久遠の花』に事情を説明して、一番知識が豊富な薬師を連れて行けば、より確実だったと思うのですが……」
「最初はそれも考えた。だが、今まで不老不死を望んで近づいた国々が、『守り葉』によって返り討ちにされている。……真っ向から行けば、毒の標的になるだけだ。それに――」
「気は済んだか、娘。話せるならこっちを向け」
突然、背後から抑揚のない声が聞こえてくる。
弾かれたようにいずみが振り向くと、いつの間にか水月を斬ろうとしていた青年が、木箱に腰をかけてこちらを見ていた。
まったく気配を感じなかった……。
得体の知れない不気味さを感じつつ、いずみは座り直して青年と向き合う。
無機質な目が、こちらを品定めするように見つめてくる。
そしておもむろに、青年は小さく息をついて腕組みをした。
「女子供は騒々しいだけだと思っていたが、お前は違うようだな。その利発さなら、我が主の期待に応えてくれそうだ」
我が主とは誰なのだろう?
聞き返そうとして、いずみは思いとどまる。闇雲に話を聞いても混乱するだけだ。
まずは順を追って話を聞こう。
いずみは乾いた唇を湿らせ、口を開いた。
「あの、貴方がたは一体何者なのですか?」
青年は目を細め、わずかに思案してから言葉を紡いだ。
「俺の名はキリル……俺たちはバルディグの偉大なる王、ジェラルド陛下に仕えている者だ」
バルディグ――大陸の北部にある国で、北方で最も厳しい冬を迎えていると噂に聞いたことがある。
あと覚えているのは、大人たちが「バルディグにはなるべく行きたくないな」と口を揃えて言っていたこと。
話を聞いた時に、理由は聞かなかった。きっと酷い寒さで行き来するのが大変なのだろう、としか考えていなかった。
いずみは唾を呑み込むと、キリルへ向ける眼差しを強くした。
「国王陛下が不老不死を望まれたから、『久遠の花』を捕らえにきたのですか?」
「ああ、その通りだ。陛下は数年ほど前から、死ぬことを非常に恐れていらっしゃる。だから『久遠の花』の伝承を聞き、何が何でも連れて来いと命じられたのだ」
キリルの話を聞きながら、いずみは手を強く握り込み、感情のおもむくままに言いたくなる気持ちを抑え込む。
「どうして力づくで私たちを捕らえようとしたのですか? どなたか隠れ里に来て『久遠の花』に事情を説明して、一番知識が豊富な薬師を連れて行けば、より確実だったと思うのですが……」
「最初はそれも考えた。だが、今まで不老不死を望んで近づいた国々が、『守り葉』によって返り討ちにされている。……真っ向から行けば、毒の標的になるだけだ。それに――」