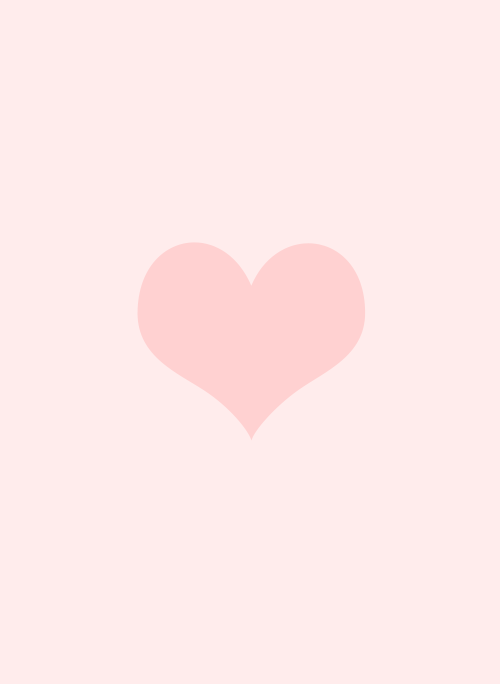「いえ、これもお仕事ですから」
けれどアタシはニッコリ笑みを浮かべて、箒を持ち上げる。
今、アタシは一人で庭の掃除をしている最中だった。
「ところで何かご用事ですか?」
「ああ、そうでした」
あの人は柔らかな笑みを浮かべたまま、アタシの側に来る。
そして耳元でそっと、
「…今夜、私の部屋に十時に来てください」
「はっはい…」
低い声で囁かれ、思わず声が裏返ってしまう。
けれどあの人はにっこり微笑んで、邸に向かう。
「ふぅ…」
…あの人と恋人になって数ヶ月は経つけれど、こういうのは慣れないなぁ。
「まっ、相手が上手ってことだけど」
アタシはメイドとして、あの人は執事として、ここに住み込みで働いている。
大学を卒業したのは良いけれど、就職浪人となってしまったアタシに声をかけてくれたのが、あの人だった。
最初はメイドなんて…と思っていたけれど、お給料が良かったので、今では自然な作り笑みも得意になってしまった。
けれどアタシはニッコリ笑みを浮かべて、箒を持ち上げる。
今、アタシは一人で庭の掃除をしている最中だった。
「ところで何かご用事ですか?」
「ああ、そうでした」
あの人は柔らかな笑みを浮かべたまま、アタシの側に来る。
そして耳元でそっと、
「…今夜、私の部屋に十時に来てください」
「はっはい…」
低い声で囁かれ、思わず声が裏返ってしまう。
けれどあの人はにっこり微笑んで、邸に向かう。
「ふぅ…」
…あの人と恋人になって数ヶ月は経つけれど、こういうのは慣れないなぁ。
「まっ、相手が上手ってことだけど」
アタシはメイドとして、あの人は執事として、ここに住み込みで働いている。
大学を卒業したのは良いけれど、就職浪人となってしまったアタシに声をかけてくれたのが、あの人だった。
最初はメイドなんて…と思っていたけれど、お給料が良かったので、今では自然な作り笑みも得意になってしまった。