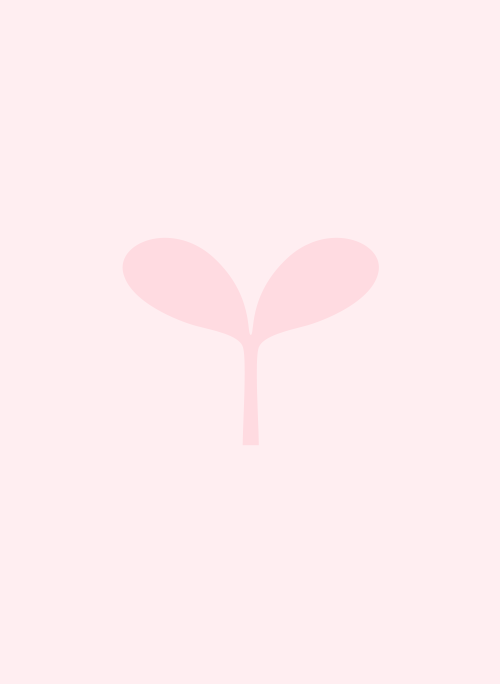拾われた日から、ちょうど十八回目の春のことでした。
育ての親であった村長が泉下の人となり、日々ぼんやりと過ごしていたときです。頼る者もなく、親しくしてくれる友人もおらず、ときおり村長を思い出しては涙をこぼしていた私のもとに、ひとりの男性が訪れてきました。
男性は、村長の息子だと告げました。
はて。確か村長に子供がいるという話を聞いたことがなかったものですから、おそらく相手にとても失礼な表情をしていたことでしょう。感情が顔に出やすいと、生前よく村長に諌められたものです。首を傾げ、私は尋ねました。
「私に用向きとはどのようなことでしょう」
「はい。婿としてあなたをお迎えにあがりました」
手にしていた竹ぼうきを、思わず手から離してしまいました。庭の桜が花びらを落とし始めたので、掃除をしていたところでした。慌ててほうきを拾い、屈んだ先で男性を見上げると、彼はにこにこと人のよさそうな笑顔を浮かべていました。
「お迎えにあがったと言っても、なにもここから連れ出そうということではありませんのでご安心ください。わたしがこちらにご迷惑になります。もちろんお金の心配はご無用です」
村長の遺品を受け取りに来たのでしょうか。それとも、血の繋がらない私をここから追い出しに来たのでしょうか。そんなことばかりを思い浮かべ、次に答えるべき言葉を探していた私は、ついに言葉を失ってしまったのです。
本音を言うと、正直戸惑っておりました。一生独り身でいる覚悟でありましたし、なにより、いま初めて会って会話という会話もなしに、夫婦(めおと)になるなど頷けるはずもありません。
ですが、どうして私が断れましょうか。
命を失うはずだった私を育てあげてくだすった村長の、その息子だという彼の言葉に、了承するしかなかったのです。