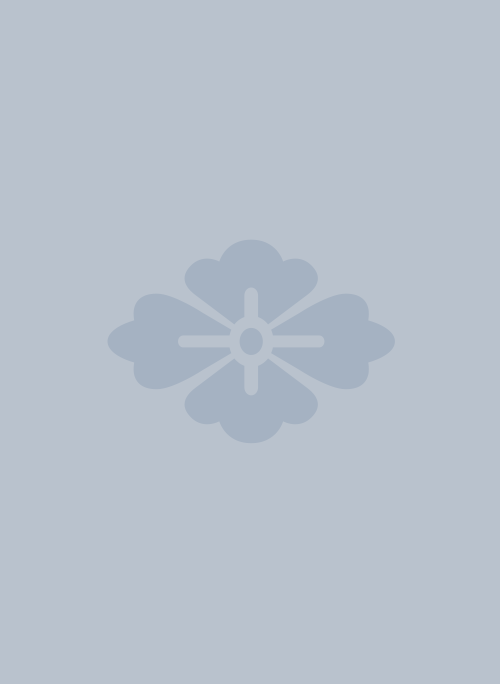そして土方さんは無言でそっと私の目じりに手を当てて残っていた涙をぬぐう。
「あっ・・・・」
「なにか嫌なことでもあったか?」
「いえ、そんなことは!!」
「じゃあなんで泣いてるんだよ。」
「・・・・夢を見たんです」
「夢?」
土方さんがあまりにも優しく尋ねるから私はおもわずすべてを話していた。
お母様が幼いころに亡くなったこと。
私の家は有名な神社で、私はお母様のように強い霊力がないこと。
そのせいで一族から邪魔者にされていたこと。
「そうか。櫻もつらかったんだな。だがな、そんなこと気にすることなんかねえ。」
「え?」
「母親は母親だ。お前はお前だ。だから、気にすることじゃねえ。」
「っ・・・・」
ずっと誰かにそう言ってほしかった。
優しい言葉をかけてほしかった。
私の存在を認めてほしかった。
私は止めることができない涙を流し続けた。
「大丈夫だ。」
そう言って土方さんは私を優しく抱きしめた。
その腕があまりのも温かくて、私はその腕にすがって泣いた。
「あっ・・・・」
「なにか嫌なことでもあったか?」
「いえ、そんなことは!!」
「じゃあなんで泣いてるんだよ。」
「・・・・夢を見たんです」
「夢?」
土方さんがあまりにも優しく尋ねるから私はおもわずすべてを話していた。
お母様が幼いころに亡くなったこと。
私の家は有名な神社で、私はお母様のように強い霊力がないこと。
そのせいで一族から邪魔者にされていたこと。
「そうか。櫻もつらかったんだな。だがな、そんなこと気にすることなんかねえ。」
「え?」
「母親は母親だ。お前はお前だ。だから、気にすることじゃねえ。」
「っ・・・・」
ずっと誰かにそう言ってほしかった。
優しい言葉をかけてほしかった。
私の存在を認めてほしかった。
私は止めることができない涙を流し続けた。
「大丈夫だ。」
そう言って土方さんは私を優しく抱きしめた。
その腕があまりのも温かくて、私はその腕にすがって泣いた。