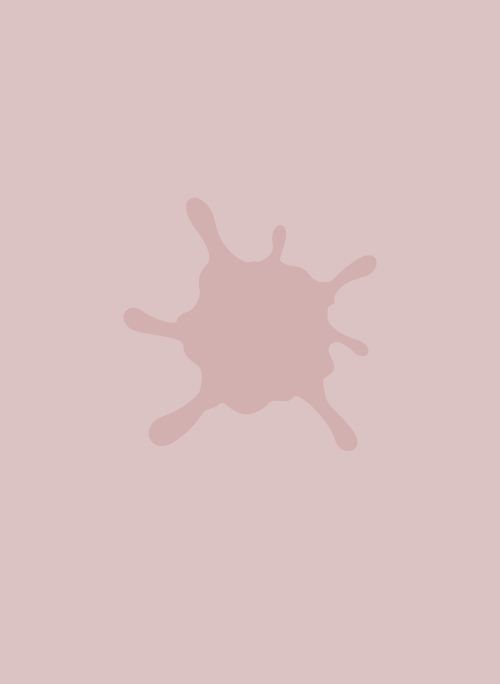「あっ、すみません! 先生の彼女さんに迷惑ですよね」
「…いや、恋人いないから」
「そっそうなんですか? 先生、モテそうなのに」
「お前達の年頃だとそう見えるのかもしれないが、いざ恋人となるとそういうタイプじゃないとよく言われる」
「そう…ですかねぇ?」
ナツキは正直もったいないと思った。
けれど言ってしまうことは、秘めたる気持ちも言ってしまうこと。
なのでタカシナから視線を逸らし、呟くだけにする。
「ボクだったら…先生が良いな」
「何か言ったか?」
「いっいえいえ! その…学校にいる先生のファンのコ達が聞いたら、喜びそうだなぁっと」
「…ナツキはどうだ?」
「えっ?」
タカシナはふと真剣な表情になり、真っ直ぐにナツキを見つめた。
「ナツキはわたしに恋人がいないこと、嬉しく思うか?」
「そっそれは…」
ナツキは自分の顔が赤くなっていくのを感じた。
「…いや、恋人いないから」
「そっそうなんですか? 先生、モテそうなのに」
「お前達の年頃だとそう見えるのかもしれないが、いざ恋人となるとそういうタイプじゃないとよく言われる」
「そう…ですかねぇ?」
ナツキは正直もったいないと思った。
けれど言ってしまうことは、秘めたる気持ちも言ってしまうこと。
なのでタカシナから視線を逸らし、呟くだけにする。
「ボクだったら…先生が良いな」
「何か言ったか?」
「いっいえいえ! その…学校にいる先生のファンのコ達が聞いたら、喜びそうだなぁっと」
「…ナツキはどうだ?」
「えっ?」
タカシナはふと真剣な表情になり、真っ直ぐにナツキを見つめた。
「ナツキはわたしに恋人がいないこと、嬉しく思うか?」
「そっそれは…」
ナツキは自分の顔が赤くなっていくのを感じた。