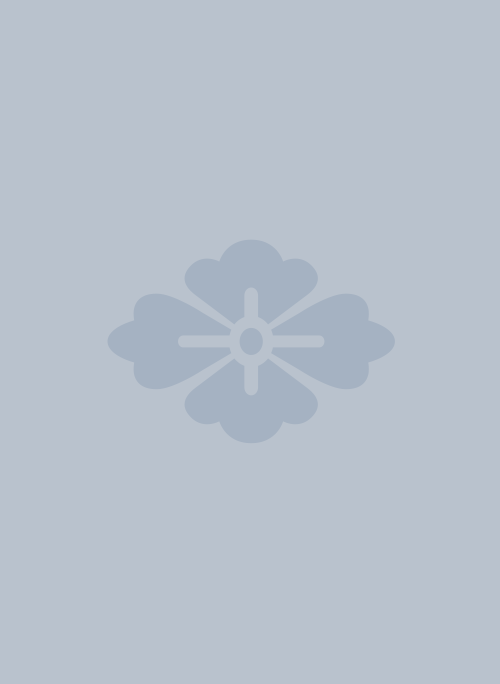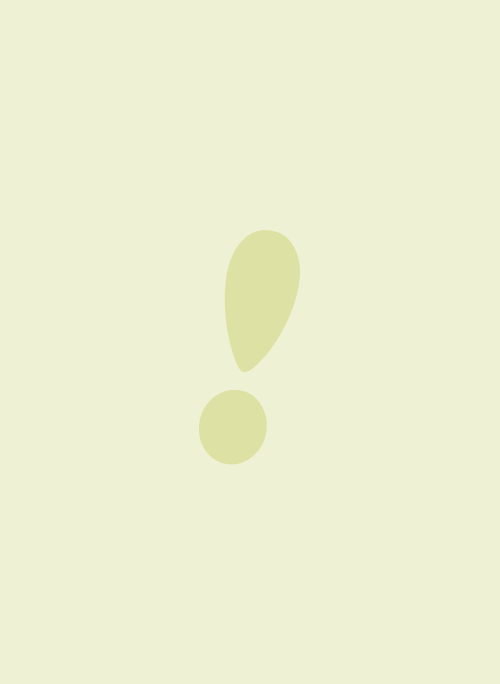「そりゃよ、何かにがむしゃらになってりゃあ、忘れちまう時もあるさ。
でもよ、そん時は、理由がわかりかけてるんだよ。
んで、ある時ハッと気付くんだ。『このために生まれてきたんだ!』ってのをよ」
「じーちゃんは、気付いたの?」
「俺の場合はな…今のばーさんと結婚した時と、息子が生まれた時と、孫が生まれた時だな」
「悠人が?」
「おうよ!あん時ゃ、嬉しかったぜー!自分が生まれた事にさえ感謝したくらいだからな」
「そっか…」
また、ポーンポーンと合図の音が鳴った。
「おっ!こうしちゃいられねえ!今頃その悠人が泣きべそかいてらぁ!」
じーちゃんは、携帯灰皿にタバコを放り込んでスクッと立ち上がった。
「昨日のカワイ子ちゃんが手伝ってくれてっから、まぁ~何とかなってるかな!」
「葵が?」
「そうさ。お前も夜になったら、みんなと花火見るんだろ?」
「オレは…悪いけど帰るよ。悠人達に伝えて」
「おっ?そうか、残念だな。まぁ、来年も来いや、な?」
オレは膝を抱えたまま、立ち去るじーちゃんを見送った。
「おい、ペイ太郎!」
自転車にまたがったじーちゃんが、デカイ声で叫んでる。
「俺はよぉ、いつポックリ逝くかわかんねーんだ。だからよ、今のは遺言だ!覚えとけよ!ガハハハ!!」
でもよ、そん時は、理由がわかりかけてるんだよ。
んで、ある時ハッと気付くんだ。『このために生まれてきたんだ!』ってのをよ」
「じーちゃんは、気付いたの?」
「俺の場合はな…今のばーさんと結婚した時と、息子が生まれた時と、孫が生まれた時だな」
「悠人が?」
「おうよ!あん時ゃ、嬉しかったぜー!自分が生まれた事にさえ感謝したくらいだからな」
「そっか…」
また、ポーンポーンと合図の音が鳴った。
「おっ!こうしちゃいられねえ!今頃その悠人が泣きべそかいてらぁ!」
じーちゃんは、携帯灰皿にタバコを放り込んでスクッと立ち上がった。
「昨日のカワイ子ちゃんが手伝ってくれてっから、まぁ~何とかなってるかな!」
「葵が?」
「そうさ。お前も夜になったら、みんなと花火見るんだろ?」
「オレは…悪いけど帰るよ。悠人達に伝えて」
「おっ?そうか、残念だな。まぁ、来年も来いや、な?」
オレは膝を抱えたまま、立ち去るじーちゃんを見送った。
「おい、ペイ太郎!」
自転車にまたがったじーちゃんが、デカイ声で叫んでる。
「俺はよぉ、いつポックリ逝くかわかんねーんだ。だからよ、今のは遺言だ!覚えとけよ!ガハハハ!!」