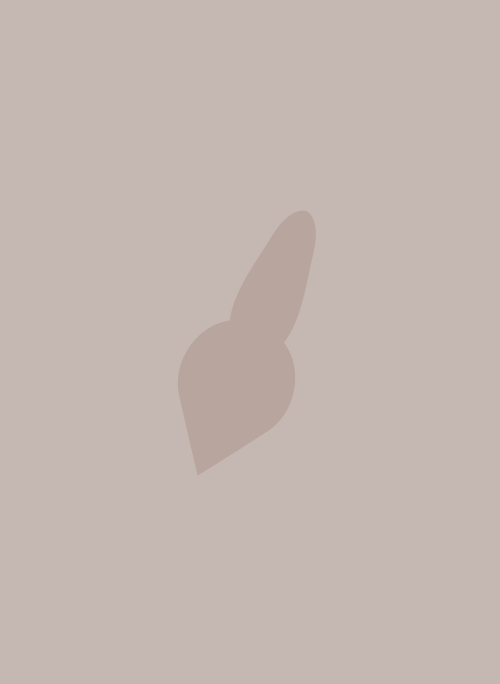そんな家に羨望の眼差しを送っていた私の腕を圭がつつく。
「都、みてよ」
圭と同じように首をそらして、天を仰ぐと、そこには儚げな光がぽつぽつと、真っ黒の絵の具を零したような空で輝いていた。
「きれい…」
「うん」
思わず漏れた呟きに、圭が頷く。
なぜだか、ふいに泣きたくなった。
「都、みてよ」
圭と同じように首をそらして、天を仰ぐと、そこには儚げな光がぽつぽつと、真っ黒の絵の具を零したような空で輝いていた。
「きれい…」
「うん」
思わず漏れた呟きに、圭が頷く。
なぜだか、ふいに泣きたくなった。