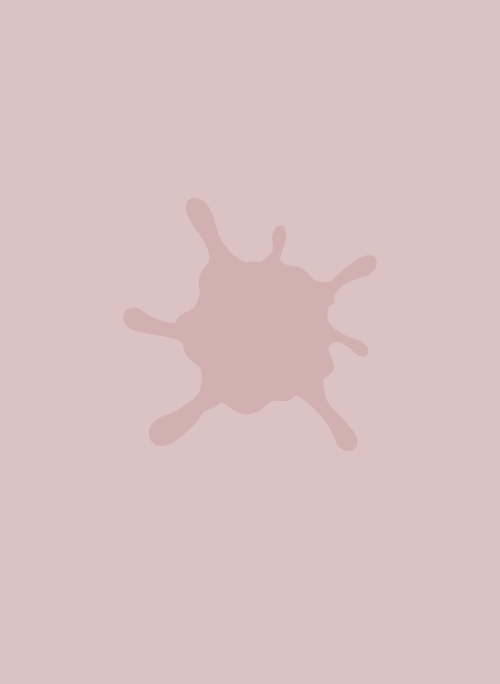しばらくして、体育館のドアが開く音がして振り向いた。
するとこそには杉村がいて、もう三十分が経ってしまったことを示していた。
時計を持っていないといっても、大体なら三十分がどれくらいの長さか分かるだろうと思っていたのだが、予想以上に体内時計は狂っていた。
わたしたちが普段、時計に頼り切って生活していることが改めて感じられた。
「さて。それでは本題に入りましょうかねぇ」
カツカツと軽快な音を立てて、杉村が演台へとのぼっていく。
わたしは気を許すことがないようにと、体を強張らせた。
「単刀直入に言ってしまうと、あなたたちは実験台となってもらいます。ああ、もちろん野宮先生もね」
くすりといやらしい笑いと共に、杉村がそう言い放った。
野宮先生というのは、もちろんわたしたちの担任の先生のことだ。
わたしたちは馴染みのない「実験台」という言葉の意味がいまひとつ分からなく、みんなで顔を見合わせあっていた。
だけどそれらの顔は不安に満ちていた。
実験台なんて言葉に希望が抱けるわけがない。
するとこそには杉村がいて、もう三十分が経ってしまったことを示していた。
時計を持っていないといっても、大体なら三十分がどれくらいの長さか分かるだろうと思っていたのだが、予想以上に体内時計は狂っていた。
わたしたちが普段、時計に頼り切って生活していることが改めて感じられた。
「さて。それでは本題に入りましょうかねぇ」
カツカツと軽快な音を立てて、杉村が演台へとのぼっていく。
わたしは気を許すことがないようにと、体を強張らせた。
「単刀直入に言ってしまうと、あなたたちは実験台となってもらいます。ああ、もちろん野宮先生もね」
くすりといやらしい笑いと共に、杉村がそう言い放った。
野宮先生というのは、もちろんわたしたちの担任の先生のことだ。
わたしたちは馴染みのない「実験台」という言葉の意味がいまひとつ分からなく、みんなで顔を見合わせあっていた。
だけどそれらの顔は不安に満ちていた。
実験台なんて言葉に希望が抱けるわけがない。