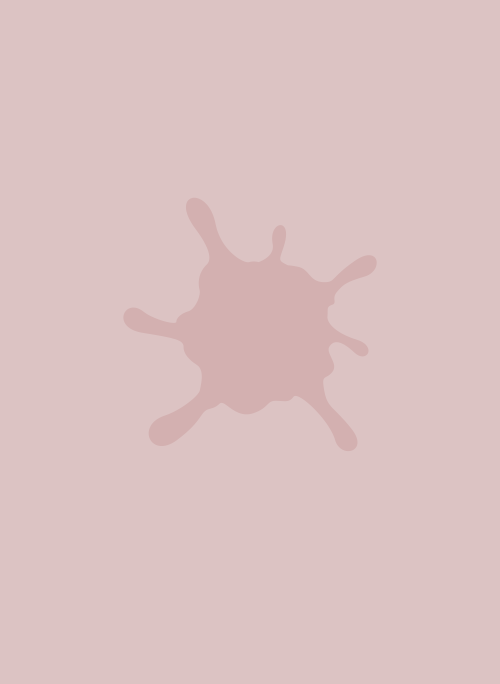「その町にはとにかく廃墟が多くって。病院やら学校やら、ガソリンスタンドにボーリング場まで。バブルが弾けた後、建物を壊すお金もなくて、そのまま放置よ」
「それは…マズイわね」
人が多くいた場所ほど、いなくなる時は始末をつけなければならない。
そうじゃないと、いろいろと良くないものが集まってしまうのだ。
「でも可哀想にさぁ。アイドルの女の子、霊感バリバリにあるコだったのよね」
クッキーをバリバリ食べながら、話を続ける姿は、あまり緊張感がないように見えるな。
「昼間っからそういう廃墟を巡らされて、イヤなモン、いっぱい見ちゃったみたい」
「でもそういう現場には、霊能力者の一人か二人は付くんじゃない?」
実際、わたしにも時々オファーが来る。
けれど夏場はイロイロと忙しいので、断っていた。
「うん。いたことはいたけど……」
彼女の表情は、失笑。
…つまり本物ではなかったのだろう。
そういうのも、また珍しくはない。
「それをまた女の子も気付いたみたいでね。ガタガタ震えていたな」
「それは…マズイわね」
人が多くいた場所ほど、いなくなる時は始末をつけなければならない。
そうじゃないと、いろいろと良くないものが集まってしまうのだ。
「でも可哀想にさぁ。アイドルの女の子、霊感バリバリにあるコだったのよね」
クッキーをバリバリ食べながら、話を続ける姿は、あまり緊張感がないように見えるな。
「昼間っからそういう廃墟を巡らされて、イヤなモン、いっぱい見ちゃったみたい」
「でもそういう現場には、霊能力者の一人か二人は付くんじゃない?」
実際、わたしにも時々オファーが来る。
けれど夏場はイロイロと忙しいので、断っていた。
「うん。いたことはいたけど……」
彼女の表情は、失笑。
…つまり本物ではなかったのだろう。
そういうのも、また珍しくはない。
「それをまた女の子も気付いたみたいでね。ガタガタ震えていたな」