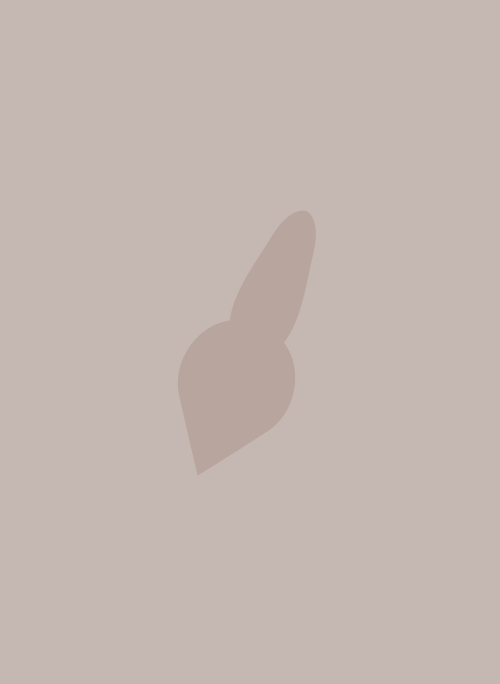でも、日々がたつにつれて、陽菜が恋しくなる。
会いたい。
会いたい。
陽菜のそばにいきたい。
苦しいくらい、禁断症状のように、そう思う。
「どうしたわけ、海老原?
あんだけ、番犬みたく福田さんの周りをうろうろしていたのに?
つきあってたんじゃなかったわけ?」
佐藤が、聞く。
「だれが、番犬だよ。うるせぇよ、どうせ、つきあってなかったし」
おれは正直にいった。
佐藤がぽんぽんと、肩をなぐさめるかのようにたたいた。
くそ・・・同情かよ。
「まぁ、陽菜さん、清純のかたまりって感じだから・・・おしまくって失敗した感じだよな。海老原、空回り???
けどさぁ・・・押してだめなら、ひいてみろっていうから、まぁ、それもいいんじゃない?
もっとも、それも陽菜さんが少しでもおまえのこと、気にしていなきゃいみないけどね」
「・・・なぐさめてるのか、それとも、おまえ、とどめさしてるのかよ?」
おれは恨みがましく、つっぷした机から顔をあげて、佐藤を睨んだ。