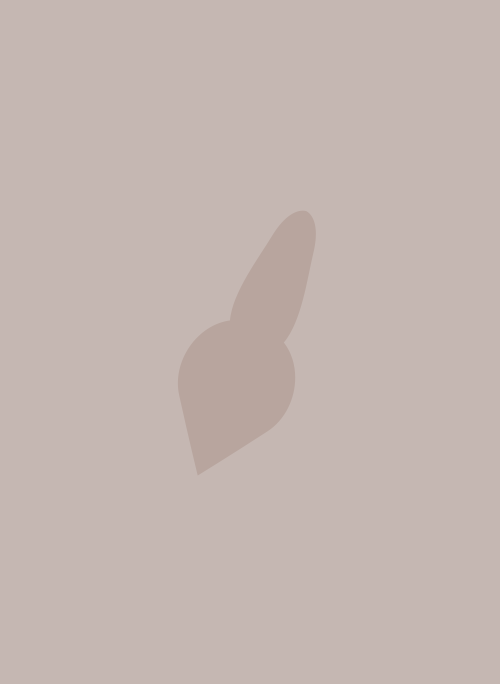「おまえ? わからない、ほんとうに、おれの気持ち?」
声が低く、のどの奥から、かすれるように出てきた。
「ひ、光くん?」
おれのただならぬ様子に、陽菜はおびえたように背中の扉に身をよせた。
その、態度がおれをますます、止められなくさせた。
逃がさない。逃がしたくない。好きだから。
たとえ、嫌われていても、それでも、陽菜を失いたくない。
おれに縛り付けてでも、逃がしたくはない。
なんで、おれの気持ちをわかってくれないんだろう?
「にぶいにもほどかあるぜ?
本当に、全然、わからない?
それに、いじめっこってなに? おれ、それもうやめたつもりなんだけど。
---それとも、いじめてほしいのか?」
おれは手をのばして、陽菜をつかまえた。
頬を押さえて、そのまま、顔を動けなくして、キスをした。
最低な、キスだ。