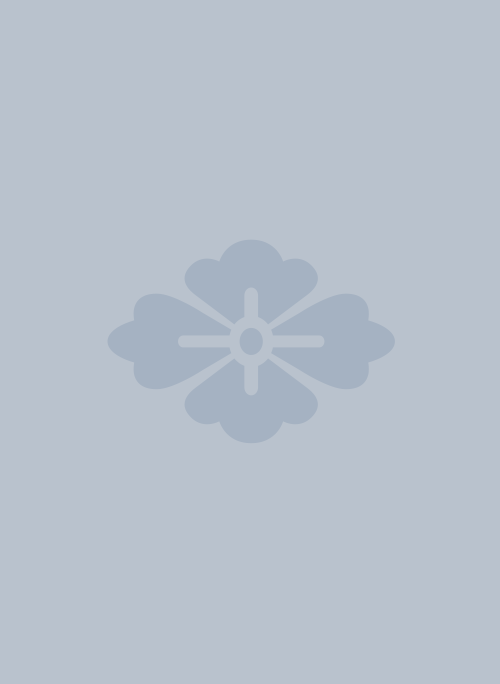『……く……そ……!』
セイラはもう一度呻くと。
凄い至近距離で、わたしを覗き込んでいた瞳を一旦、ぎゅっと閉じ、次に目を開いた。
その瞬間。
瞳の片方が、いつもの琥珀色に戻る。
「星羅……っ!?」
わたしの声が、届いたのかどうか。
ソファベッドの上で、わたしにのしかかっていた星羅が、のけぞるように離れた。
そして、彼は、よろよろと立ち上がると、まだ赤く光っている方の瞳を両手で押さえて、呼んだ。
わたしの名を。
「……真……衣……!」
『ヴェ…リ…ネ…ルラ』
聞き慣れた、星羅の声に重なるようにして、別の声も聞こえ……た?
セイラはその蒼く長い髪を振り乱して、カラダを丸めると、低くささやいた。
「この……っ! 真衣が……泣いてる……!!
お前は……っ!
僕の中から出て行け……!」
『くそ……!
俺様だって、てめーなんざ……っ、大嫌ぇだ!!!
ヴェリ……ネルラ……も……泣かす気なんざ……ねぇ!!』
まるで、一つのカラダに二人分の魂が入り込んで、ケンカしているみたいだ。
やがて、器になっている蒼いセイラのカラダが、ファミレスで狼の腕を見せた時と同じように輝いた。
セイラはもう一度呻くと。
凄い至近距離で、わたしを覗き込んでいた瞳を一旦、ぎゅっと閉じ、次に目を開いた。
その瞬間。
瞳の片方が、いつもの琥珀色に戻る。
「星羅……っ!?」
わたしの声が、届いたのかどうか。
ソファベッドの上で、わたしにのしかかっていた星羅が、のけぞるように離れた。
そして、彼は、よろよろと立ち上がると、まだ赤く光っている方の瞳を両手で押さえて、呼んだ。
わたしの名を。
「……真……衣……!」
『ヴェ…リ…ネ…ルラ』
聞き慣れた、星羅の声に重なるようにして、別の声も聞こえ……た?
セイラはその蒼く長い髪を振り乱して、カラダを丸めると、低くささやいた。
「この……っ! 真衣が……泣いてる……!!
お前は……っ!
僕の中から出て行け……!」
『くそ……!
俺様だって、てめーなんざ……っ、大嫌ぇだ!!!
ヴェリ……ネルラ……も……泣かす気なんざ……ねぇ!!』
まるで、一つのカラダに二人分の魂が入り込んで、ケンカしているみたいだ。
やがて、器になっている蒼いセイラのカラダが、ファミレスで狼の腕を見せた時と同じように輝いた。