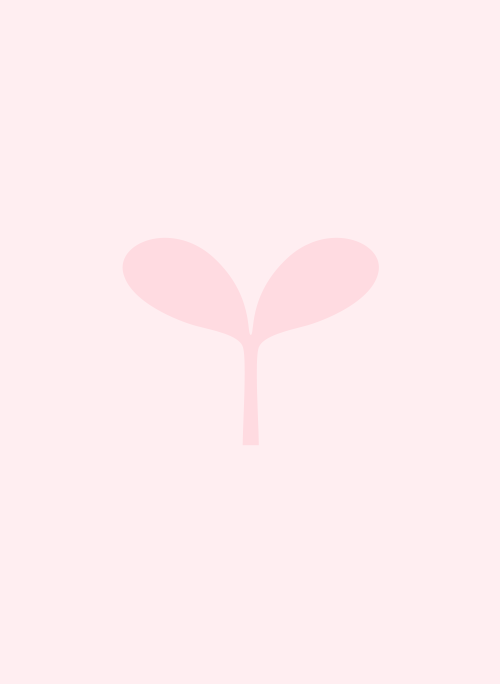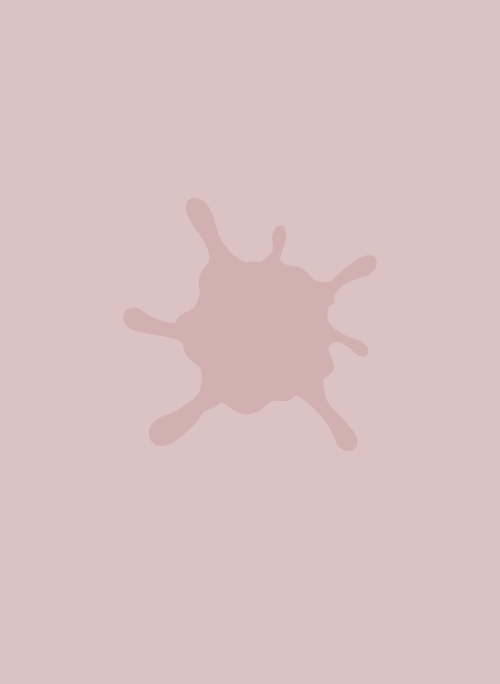いつ晴れるか分からない、濃い霧を前に、木暮と西郷の二人は諦め、いつしかカードを始めた。
カードは西郷が持っていたようだ。
黛には、ポーカーゲームをしているのだと、すぐに分かった。
「私は二階にいます。何かありましたら、声を掛けて下さい」
「ああ、わかった」
「もしかしたら、ちょっと篭るかもしれませんが、すみませんね」
「ああ、分かってるよ」
「お仕事なんでしょう。頑張って下さいね」
木暮が顔を向けずに応対する西郷に変わって、にこやかに答えた。
二人は時間を忘れて、ポーカーゲームに磯染んだ。
いつの間にか、寝食をも忘れて夕方になっていた。
「ああ、負けた負けた」
「すみません。ツキがあったようで」
「いや、楽しかったよ」
「私も楽しかったです」
二人は暫く余韻に浸っていた。
西郷が大きく溜め息を着いたあと、ふと、二階に目をやった。
「作家センセイは執筆中だな」
「調子がよいのでしょうね」
「物音ひとつしないな」
「書くのにそんな音はしませんよ」
「でも、昼メシ食べてないぞ」
「そうですね」
「様子を見に行こう」
「邪魔したらマズイですよ」
「差入だよ」
西郷はそういって、木暮に珈琲を入れさせた。
カードは西郷が持っていたようだ。
黛には、ポーカーゲームをしているのだと、すぐに分かった。
「私は二階にいます。何かありましたら、声を掛けて下さい」
「ああ、わかった」
「もしかしたら、ちょっと篭るかもしれませんが、すみませんね」
「ああ、分かってるよ」
「お仕事なんでしょう。頑張って下さいね」
木暮が顔を向けずに応対する西郷に変わって、にこやかに答えた。
二人は時間を忘れて、ポーカーゲームに磯染んだ。
いつの間にか、寝食をも忘れて夕方になっていた。
「ああ、負けた負けた」
「すみません。ツキがあったようで」
「いや、楽しかったよ」
「私も楽しかったです」
二人は暫く余韻に浸っていた。
西郷が大きく溜め息を着いたあと、ふと、二階に目をやった。
「作家センセイは執筆中だな」
「調子がよいのでしょうね」
「物音ひとつしないな」
「書くのにそんな音はしませんよ」
「でも、昼メシ食べてないぞ」
「そうですね」
「様子を見に行こう」
「邪魔したらマズイですよ」
「差入だよ」
西郷はそういって、木暮に珈琲を入れさせた。