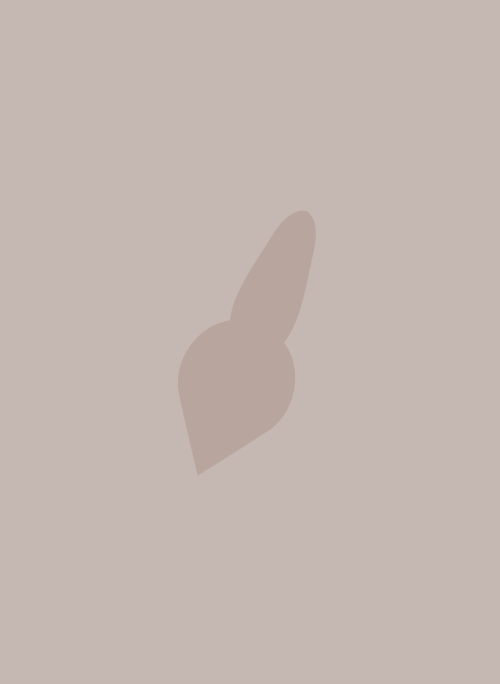「やっぱりあの傷は雀陽の仕業だったのか・・・」
「雀陽?雀陽とは誰だ?」
僕らは神主に雀陽について知っていることを述べた。
「なんと、全国を支配すると・・・!」
神主は驚いたように目を見開き、顔を上げた。そして再度俯き加減になりながら話す。
「でも、このままだと全世界が洗脳されてもおかしくない状況といえる。つまり、今の段階で何とかしなくてはならないのだが・・・」
「その刃の情報さえ解りゃあいいんだけどねー」
黄梅が腕を頭の後ろで組みながら話す。
その時、僕はふと朝の木南との会話を思い出した。
『もしかして、あの刃』
あの時、僕らは雀陽が人々を洗脳しているとも知らなかったし、ましてや洗脳の道具の一つとして刃が使われていたことなど知る由もなかった。
しかし、彼女はそれを把握していた。
一体、彼女は何者なんだ?
「神主さん、古文書とかありますか?この村に伝わる、伝奇物語とか・・・」
「探してみるか。それと、私の名前は三柱能上と言う。神主ではなくそちらの名前で呼んでもらって構わないよ」
そして三柱さんが神社の奥に行き、資料を探しに行った。僕は布を少しめくりあげ、外の様子を伺う。相変わらず、洗脳された人々が武器を持ちながらフラフラと歩いている。
これでは出るに出られない。
「二人とも・・・どこに行っちゃったんだし・・・。マジ・・・心配・・・」
黄梅は半泣きになりながら、服の裾をギュッと掴んだ。そうだ、彼女は親友と大事な祖父が消えてしまったんだ。僕ら以上に辛いものがあるだろう。
「少し、見ずらいが古文書があったぞ」
三柱さんは少し大きい巻物を出してきた。およそ百年くらい前のものらしい。
「ええと・・・その昔、鹿狩りに出かけた地位のある方が帰りに雨に降られ、この地にある水車小屋を訪れ、蓑を貸してくれと望んだところ、山吹の枝を一本渡された。このとき、このお偉いお方は激怒したらしいが、その後、それが昔の和歌の引用で、彼女が蓑もない貧乏暮らしであることを知ったそうだ。それで、そのお偉いさんは彼女を江戸に招き暑い待遇をした・・・と書かれている」
巻物の第一章を三柱さんは読み上げた。