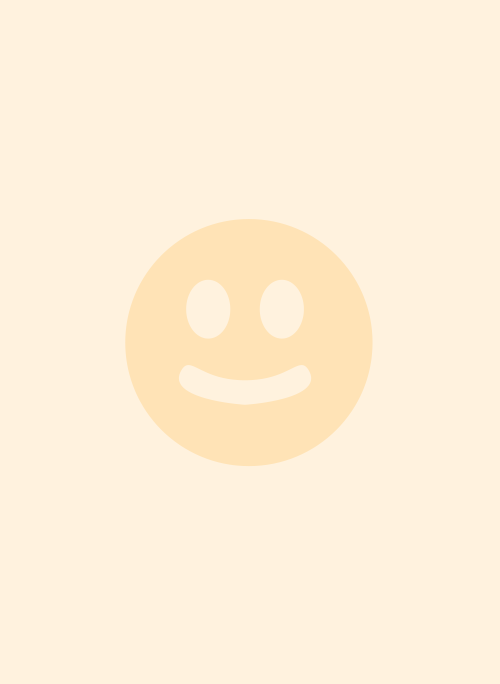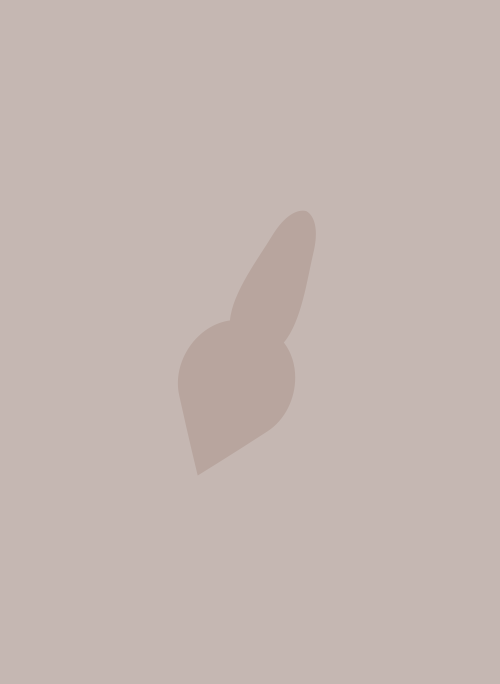「さて、そろそろごちそうさまするか」
「話の続きもしなきゃいけないしね」
ちょうど食べ終わった時にそういわれ、自分以外がもう食べ終わっていたのに気付いた。
あ、待っててくれたんだ・・・
申し訳なさで少し俯いてしまう
「興時、すまんが皿下げてくれるか?」
「了解です」
無駄のない動作で皿を片し、興時さんは部屋から出て行った。
「さてと、碧辛かったら答えんでええ。
さっきの、なんでああなったんか分かるか?」
さっきの、とは急な頭痛と訳の分からない恐怖で混乱したことをさしているなのかな
「正直ちゃんとしたことはわからないけど、頭が割れるくらいに痛く なって怖くなった」
「儂らがどっか行く思うたんか?」
どこかに行くとかじゃない、
多分あれは僕を怖がり気味悪がってまるで逃げたような感じだった
あの瞬間、
僕は見捨てらた気がした
それはとてもリアルに感じられた
まるで、そういう事があったかのように
「嫌われたかと、思ったんだ」
小さな声で呟けば
父さんも朔夜さんも苦い顔をした