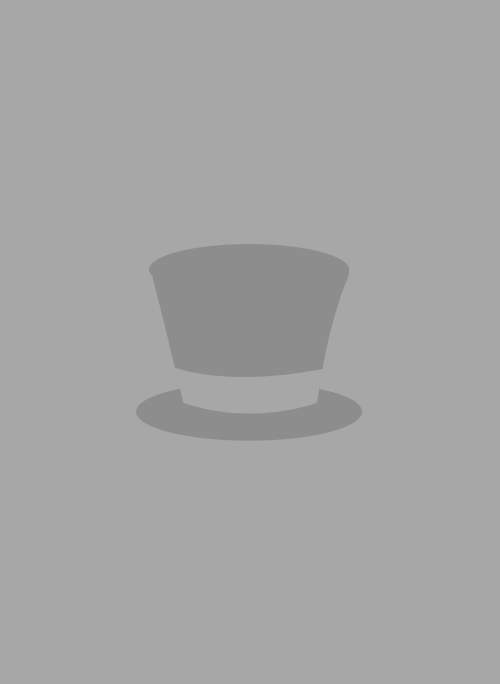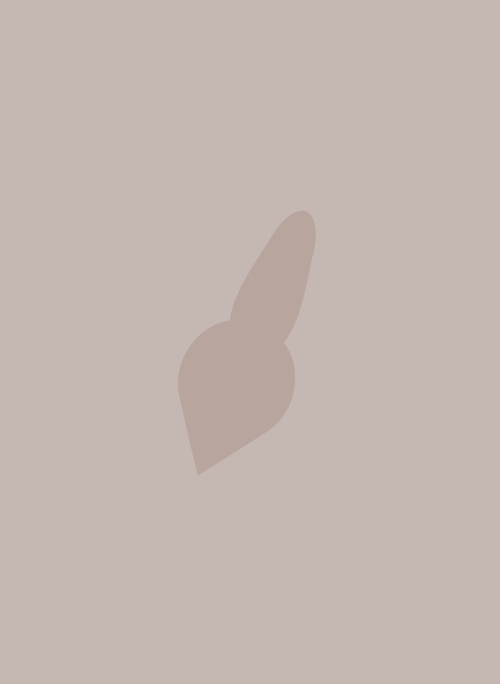そんな周りは好き勝手にやっている中、ドームの中心では火鳥が1人竜騎の側で辺りの監視を続ける。
火鳥は様々な話をして、幼い彼を不安がらせぬようにしていた。
「火鳥よ……お前の話は面白いが、余に気を使わなくても良い。そろそろ本題を話せ。その無に帰す者とやらのな」
子供ながらに少し小生意気だが、強がっているようにも見えた。
「……と言っても話したくても話せないんだよ。実際ウチらが見たこともないから話しようがないのさ。あくまで先代達から伝わった話だから。唯一、知っていたであろう竜騎はもう居ないしね」
そう言うと、火鳥は少し寂しそうな表情を浮かべた。
無理もない。
己の手で彼を消滅させてしまったのだから。
前の竜騎はもう居ない。
この話を知るのは、四獣霊の中で誰も居ないのである。
「……まあ、実際本当にそんなヤツが居たとしても、余がいる限りは好きにさせぬぞ。何て言ったって、余は『青龍』を受け継ぎし四獣霊なんだからな」
普段ならここで、亀咲に『お前に何が出来るんだ』と頭を小突かれる所であるが、反対に火鳥は竜騎の頭を撫でた。
「アハハ、そうだね♪竜騎は強いね。俺も守ってもらおうかな」
竜騎からしたら頭を小突かれるより、子供扱いして撫でられる方がプライド的にも嫌だった。
「止めろ火鳥。てい!」
手を跳ねのけ、自分の偉大さをアピールするように強く言い放った。
「余は一人前だ! それは下部である礼子が一番分かっている! 火鳥。礼子を呼んでこい!」
「駄目だよ。俺がここから離れるわけにもいかないんだから」
竜騎は緊張感も通り過ぎている。
暇である事から、自分を立ててくれる彼女を呼んで来いと言い続ける。
「でも礼子ちゃんも見回りしてるんだよ?」
「いいじゃないか、あの貧乏面した霊とアホ猫の2人で警備させていれば!」
どうやら竜騎は、皆がカワイイと言う眠り猫でも好かないようだ。
背の勝負でギリギリ負けて、上から目線に頭を撫でられたらから気に食わないのであった