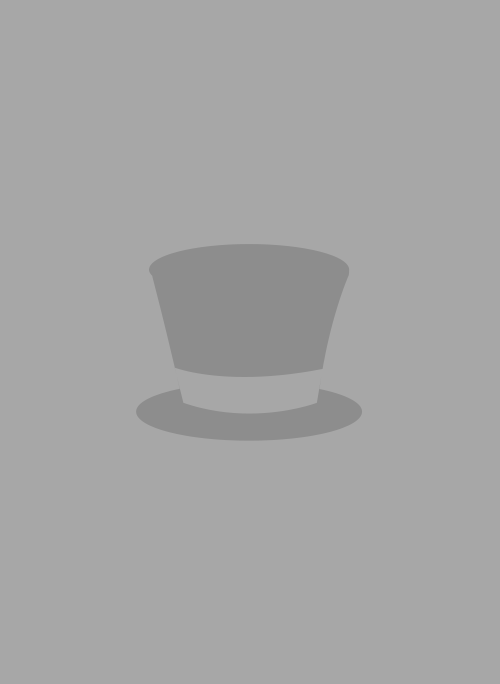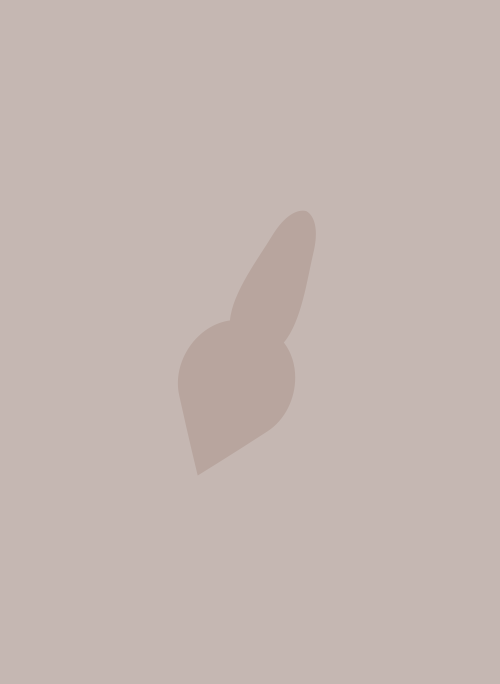「雫? 帰ってきてますの?」
すると、今まで素振りをしていた腕がピタリと止まり、ゆっくりと呼吸を落ち着かせた。
「はい。お母様」
日差しが道場の小窓から差し込み、その長い黒髪が光に照らされた。
強い夏の光に外はしっかりと映し出されているが、それとは対照の薄明るい道場の真ん中に、1人の女の子が凛として立っていた。
雫(しずく)と呼ばれた女の子は母親に呼び出されて、道場から離れた家の茶室に座らせられた。
茶室と言っても本格的に茶をする場所ではなく、ただ畳があるだけで、ここはこのように正座をして気持ちを落ち着かせる場所に使っていた。
そこで、母と対面に座り合い、先に雫は口を開いた。
「用件は何? お母様」
それだけ言うと、母はいつもと同じ台詞を言葉に出した。
「雫。アナタに合う相手を見つけてきたわ。そろそろ腰を据えて、落ち着いてちょうだい」
これは、耳にタコを通り越してイカが出来るくらい聞かされている言葉。
毎度毎度、同じ事ばかりしか言わない。
要は、お見合いをしろと言う話だ。
雫は目を軽く閉じ、ゆっくりと返事を返した。
「お母様。何度も言っているでしょう。私はまだ高校二年生ですよ? お見合いだなんて、早過ぎます」