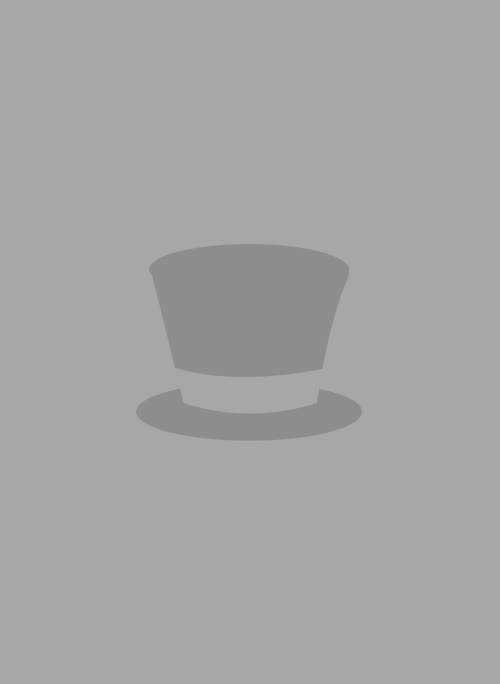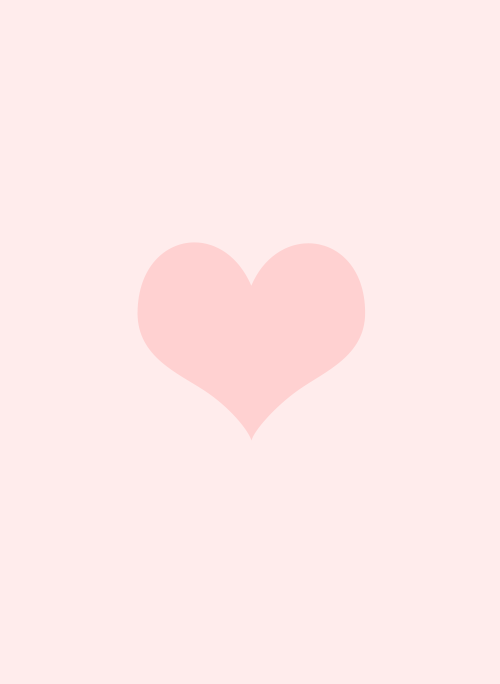身体中が汗ばんでも、
石を投げることをやめられなかった。
この苦しい思いを、
どうにかして昇華したかった。
「もう、このあたりの石がなくなっちゃうわよ」
呆れたような声。
「望むところだ」
日も暮れて、川面が闇で見えなくなっても、
俺は石を投げ続けた。
「新明くん」
そんな様子が異様に映ったのだろう、
おまえは俺の腕をそっとつかんで、
「今日はもう、帰ろ…ね?」
と言った。
俺は息がきれている自分に、そこでやっと気がついた。
「…ああ、そうだな」
一緒に土手に上がる。
「今夜は旦那は帰ってくるのか?」
そう聞いてしまいそうだった。
毎回、こうだ。
気になって仕方ない。
聞いたところで、俺にはどうすることもできないんだがな。