にへっと濡れたティッシュのごとくふにゃふにゃな笑みを浮かべる彼、カナト。
その存在が、私がファンタジー世界の住人になってしまったという証拠でもあった。
「ってかあんた、そんなシャツ着てた?」
そんなカナトが現在身に纏っているのは、薄い水色のYシャツ。
リーマンがよく着ているやつだ。そして私の父がよく着ていたやつでもある。
「サクハ君が命じたんじゃないか」
隣の部屋からシャツ持ってこいって。
その言葉は、夢が夢じゃないことを裏付けるものとなった。
よし、これから夢を現実だと認識しよう。
そして今度夢遊病についても調べておこう。
あと精神科。私はとことん疑うのをやめない人間だった。
「…………サクハ君」
「……………………なに」
寝ぼけ眼をこすりながら、呼びかけに応じる。
もうこうなったらどうでもいい、と人生自体を諦めつつ。
「その、に、人形? は何だい?」
「父さんが旅の土産に持ってきた。どこの何なのかは知らない」
まあ、他のもだけどね。
あくびを噛み殺し、父について語る。
私の父は、自称夢を追う旅人の平社員(いわゆるサラリーマン)だった。



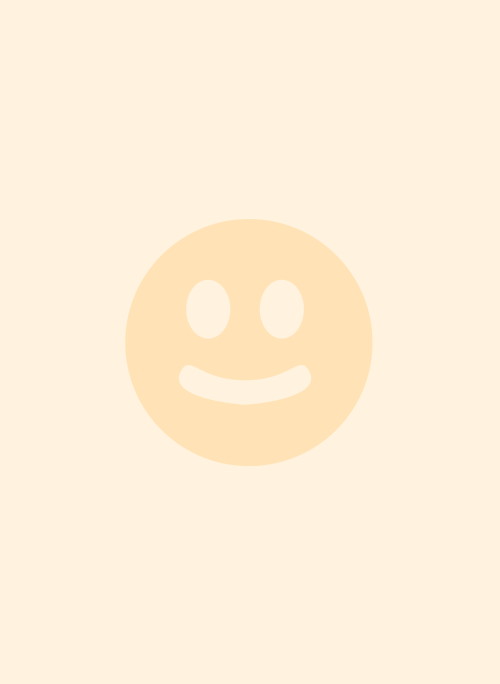
![[百合]円還恋心](https://www.no-ichigo.jp/assets/1.0.820/img/book/genre1.png)
