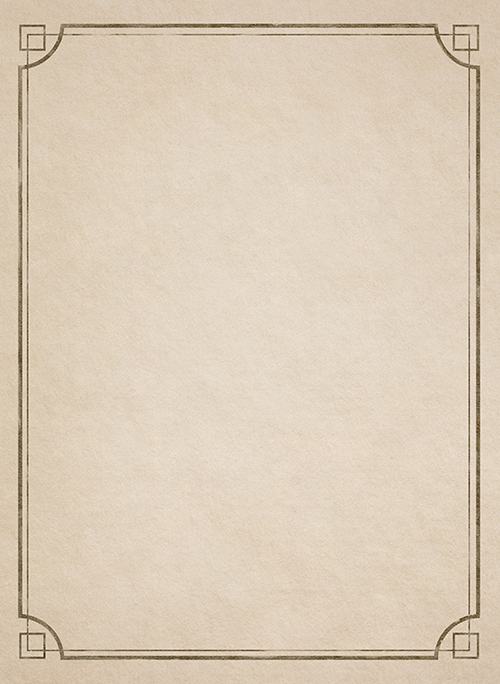「残念だったな。僕は君に愛どころか感謝のひとつも抱いたことがないんだ。耳障りで悪夢になりそうな発言は、控えるか、僕のいない…否、僕の存在しない次元でしてくれるか?」
少年は驚いた顔の青年を睨んだ。
「でも、ボスは艶を生かしたいと願った俺の意見を」
「聞いてない。耳にも入れていない。
こんな言葉で君への抱いてもいない感情を否定できるならいくらでも送る。
つまらない勘違いは夢でしてくれ。
僕は君と違って忙しい。よって君に構う時間なんか存在しない!
さぁ、出て行け。
僕の前から消えてくれ。髪の一本も残さず塵にされたくなければ、僕の前に存在するな」
凄まじい嫌われようである。
実際、少年にとって今の青年と接することはストレス以外の何者でもないのだ。
一瞬の迷いもなく追い出したい衝動を抑えきれず、少年は青年を睨んだ。
それはもう、刺す様に。