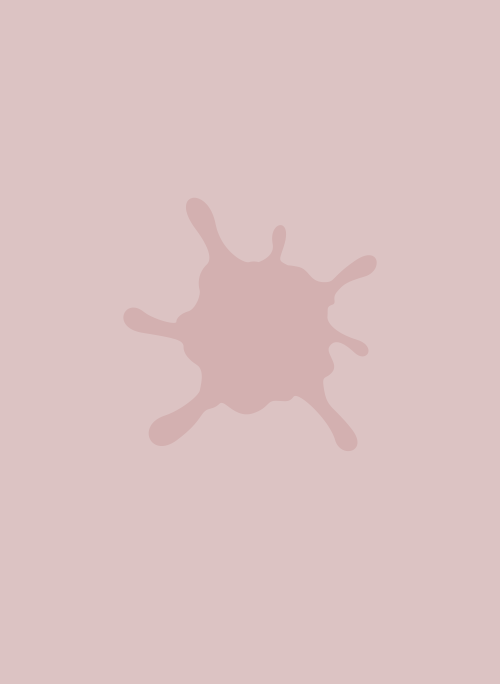そんなとき、後ろで
「そういえばさ、お前好きな人いるんだって?」
思わぬ話題に、わたしは思い切り振り返った。
後ろには、携帯を片手に微笑むお兄ちゃんがいた。
有希にメールでもしているのだろうか。
その行為はもっと有希を苦しめるものだというのに。
「誰に聞いたの?」
わたしはあえて素っ気無く答えた。
この話だけは、お兄ちゃんとしたくなかった。
わたしは手を組みながら、お兄ちゃんの返事を待つ。
「有希だよ。ほら、昨日来てたじゃん。あのとき、お前の話題が出てな」
どくり、どくり。
そんなわたしの胸の音が聞こえたような気がした。
「なあ、教えろよ。どんなやつなんだ? お兄ちゃんに秘密で付き合っちゃ駄目だぞぉ」
その胸の音は段々とひどくなり、わたしを唸らすような大音量となる。
そして、わたしの中の何かが爆発する。
「五月蝿い!」
気付けばわたしはソファから立ち上がって、お兄ちゃんに叫びかかっていた。
お兄ちゃんは面食らったような顔をしている。
気付いたときにはもう遅い。
いつもこの展開だ。
わたしはしまったという後悔に襲われる。
だけど、怒りは抜けない。
まるで今のわたしは、今日の有希みたいだと他人事のように思った。
「そういえばさ、お前好きな人いるんだって?」
思わぬ話題に、わたしは思い切り振り返った。
後ろには、携帯を片手に微笑むお兄ちゃんがいた。
有希にメールでもしているのだろうか。
その行為はもっと有希を苦しめるものだというのに。
「誰に聞いたの?」
わたしはあえて素っ気無く答えた。
この話だけは、お兄ちゃんとしたくなかった。
わたしは手を組みながら、お兄ちゃんの返事を待つ。
「有希だよ。ほら、昨日来てたじゃん。あのとき、お前の話題が出てな」
どくり、どくり。
そんなわたしの胸の音が聞こえたような気がした。
「なあ、教えろよ。どんなやつなんだ? お兄ちゃんに秘密で付き合っちゃ駄目だぞぉ」
その胸の音は段々とひどくなり、わたしを唸らすような大音量となる。
そして、わたしの中の何かが爆発する。
「五月蝿い!」
気付けばわたしはソファから立ち上がって、お兄ちゃんに叫びかかっていた。
お兄ちゃんは面食らったような顔をしている。
気付いたときにはもう遅い。
いつもこの展開だ。
わたしはしまったという後悔に襲われる。
だけど、怒りは抜けない。
まるで今のわたしは、今日の有希みたいだと他人事のように思った。