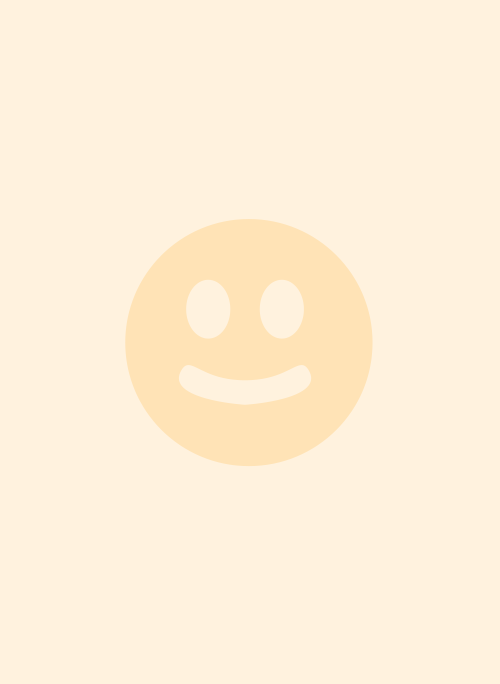碧の声がすぐ近くで聞こえて、ようやく自分から距離を縮めていたことに気付く、間抜けな私。
「わっごめ…!」
そんなつもりじゃなかった、と焦って碧から離れる。
しかしそれをさせないのが、
『で、分かったわけ?』
碧の鋭い瞳と、力強い腕。
半歩下がった私の腕を引いて引き寄せ、腰に手をまわした。
「わ、わ、分かんない…!」
残念ながらまだ理解が出来ない。
碧のいう、誘う、の意味が。
『ふ〜ん…』
碧はニヤニヤと私を探るような目で見てくる。
まるで私が何か隠しているような、それを疑っているような、そんな目で。
加えてベットに腰掛けてるせいで私よりあたまが低くなった碧は上目遣いでそれを続け、とても近い距離で、碧の体温を感じながら、見上げられるという慣れない状況。
私を再び混乱させるには十分すぎる状況だった。
「ほんとに、…分かんない…」
きっと今は、どんなに簡単な足し算だって解けやしない。
頭の中が、碧で満たされてる。
目の前にいる碧の事しか考えられない。
それぐらい私は碧によって、碧の事だけで、支配されてしまっている。
『…こういうこと』
頭のつぶやきを最後に私の視界はぐるりとまわり、ぼふんとベットに身を預けてしまった。
一瞬何が起こったか分からなくて、真っ白になってしまった頭で必死に考えた結果やっと、視界がまわる直前に碧に強く腕を引っ張られたことを思い出して、この体制は碧のせいだという事が分かった。
『お望みどおり答えをやるよ』
頭上から降ってきた声は、私に確信を齎した。