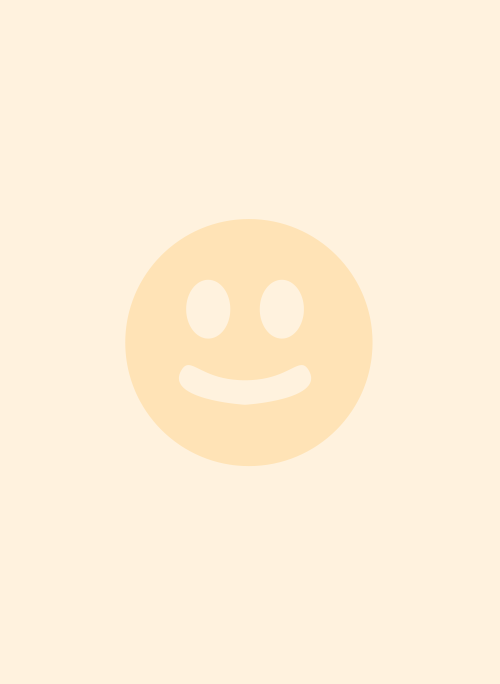涙は、止めようと思って止まるものでもなく。
拓真さんが私を見ているのに、頬を伝う涙はながれつづける。
「これはそのっ…」
どうにか弁解しようと思っても震えている今のままの声ではそれも虚しくなるだけ。
涙を必死で拭っていると、頭に何か優しい感触。
それは、
『よしよし』
紛れもなく拓真さんの手で。
暖かくて、なんだか優しくて。
涙は止まるどこるか、さっきよりも増してあふれる。
『君は碧君が好きなんだね』
安心しきってしまった私の心は、そんな拓真さんの問いに、素直に頷いてしまったんだ。
私は、碧が好きなんだ。
執事だとかそんなことは関係なくて。
男として見るなとか、主人だとか、そんなの言われたって無理なもんは無理な話で。
この涙が何よりの証拠。
でも、
「碧には言わないで下さいっっ…」
この想いは、固く閉ざして、心の中にしまっておかなくちゃ。
伝わったら最後。
きっと今の関係ではいられない。
近くにいることさえ叶わない。
それだけは嫌。
『言ってやるもんか』
そう言った拓真さんの真意は分からなかったけど、碧に伝わらなかったらそれでいい。
近くにいれたら、いいから。