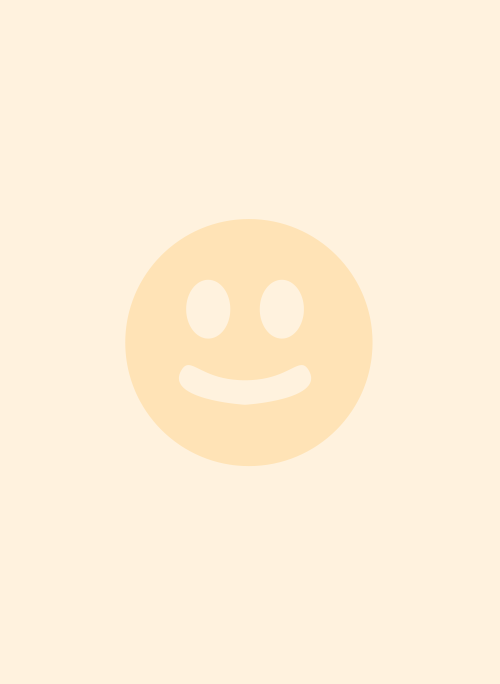『執事君、ちょっといいかな』
『紀津様が私風情に何か御用でしょうか』
『あぁ、とても大事なね』
私がお手洗いにいってる間に、事は進みだしていた。
『お嬢様がお戻りになる前に。どうか手短にお願い致します』
私は、執事の碧なんて本当は好きじゃないの。
『分かった』
でもそれが、私と碧を繋ぐ唯一の糸だから。
『僕は昔から君達を知っているけど…、いつから関係が今のようになった?』
『どういった意味でしょうか』
私はそれが切れないように、必死に思いを出さないように取り繕うの。
『昔はとても仲が良さげだったじゃないか』
『子供、でしたので』
糸がほつれてしまわないように。最後の希望が消えないように。
『しかし、どうしてそのような事を』
だからどうか、
『いや…椿さんを見る君の目がときたま、愛しい人を見る目のようだから』
「あら?、拓真さんと碧…何して…」
『てっきり君は椿さんを好きなのかと思ってね』
「…!!」
私の希望を、踏み躙るような、馬鹿だ目を覚ませと払いのけるような、そんな事しないで。
『…それは誤解です。
私はお嬢様に従うことはあっても、お慕いする事はあり得ません』
だけど聞えてしまった二人の会話は、私の希望をえぐりとるようなものだった。