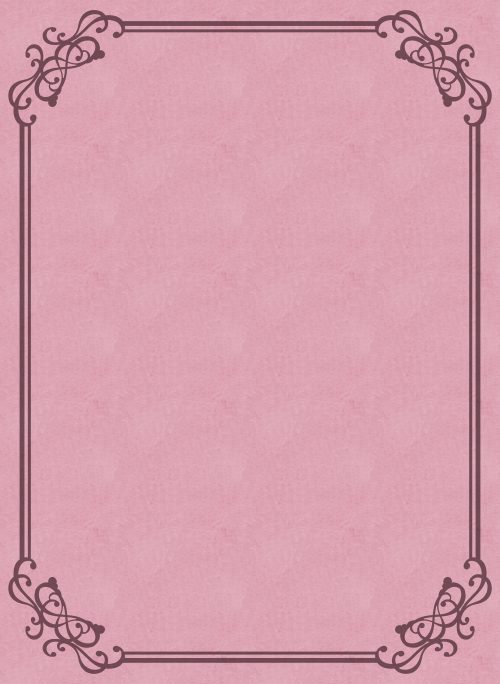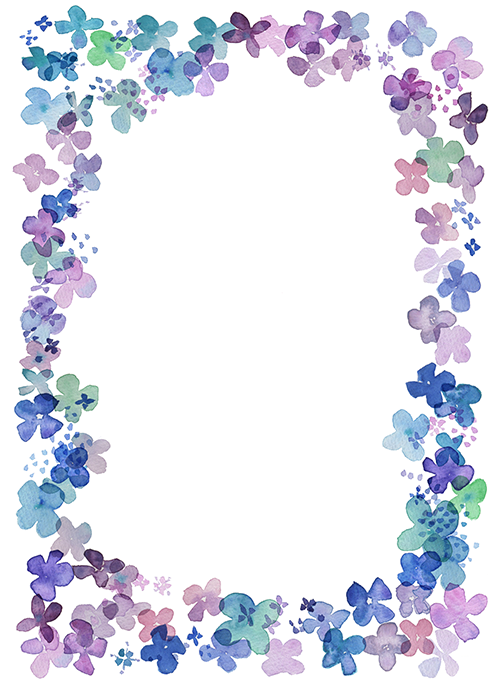「すみません、サクラさん。オレ、そろそろ…」
顔を上げると、気まずそうな顔をしたハル。
目が合わないのは、彼の意図なのだと悟ったあたしは、
「あっうん。あたしも、これから用があるから」
と咄嗟の嘘をついた。
それは最高につまらなくて、とても格好の悪い意地。
わかってる。
自分でもちゃんとわかってるんだけど、そうするしかできなかった。
軋むように胸が痛むのに、無理に笑顔を作るしかなかった。
「じゃあ、さよなら」
「じゃ……バイバイ」
『また会社でね』
浮かんだその一言を飲み込んで、背中を向けた。ハルよりも先に。
人の波が、冷たい風のように傍らを過ぎていく。
あたしも乗り遅れないよう、一歩前へ踏み出した。